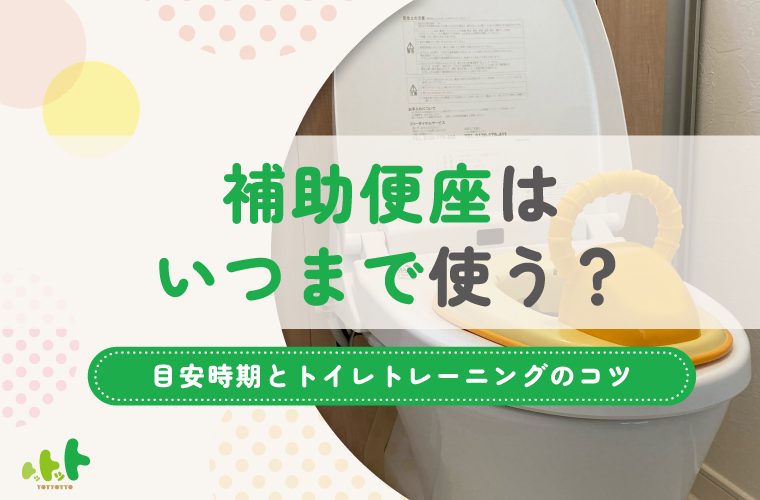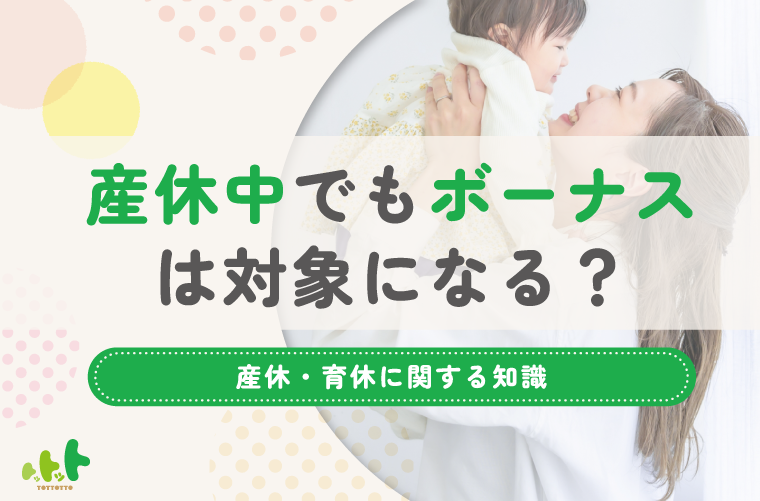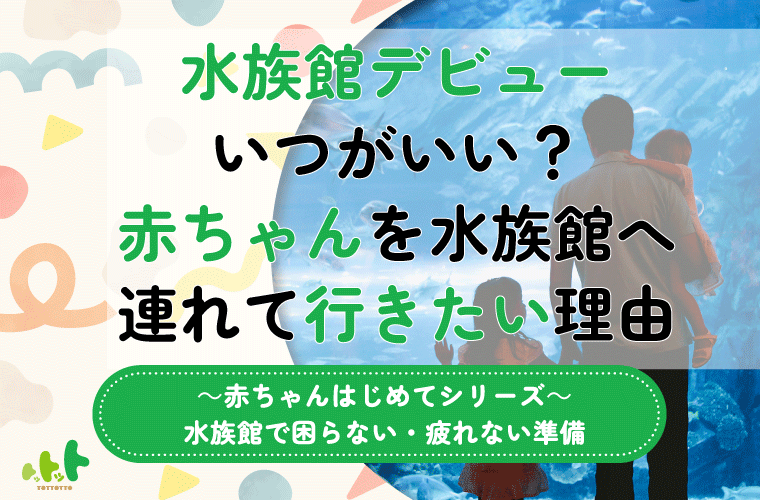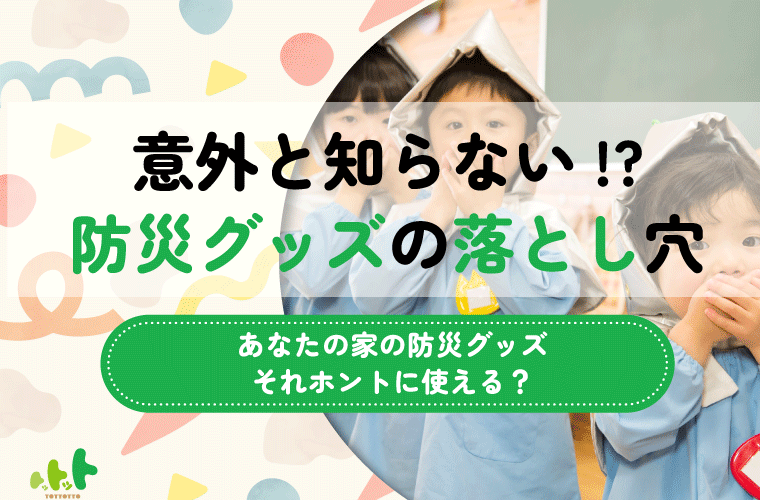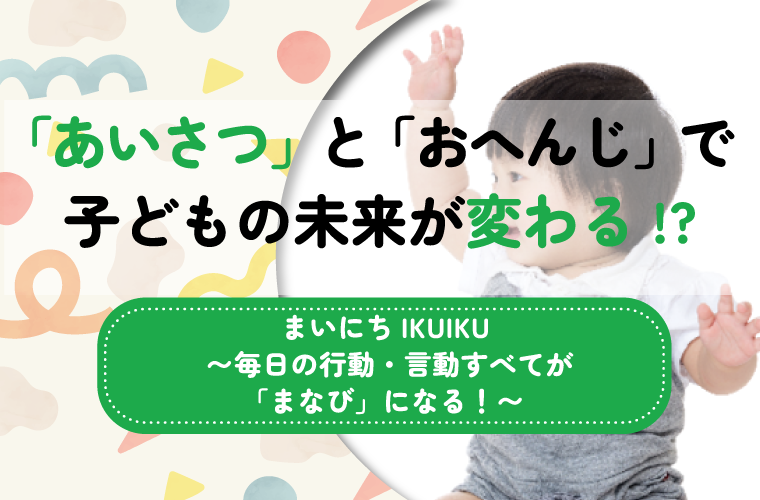赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て

子どもの自己肯定感を上げるコミュニケーションで悩んでいるママやパパも多いのではないでしょうか?
自己肯定感を上げること(=子どもが「できる!」と思えるようにすること)で、将来的に自分で問題を解決したり、困難を乗り越えたりすることができるようになります。
ただ、子どものためを思って行動していても、寄り添うことができずに無理強いさせてしまい、悩んだこともあるでしょう。
子どもとのコミュニケーションは以下のような良い影響を与えます。
- 信頼関係の構築
- 自己肯定感の向上
そのため、親子間のコミュニケーションは非常に重要です。
本記事では子どもの発達段階にあわせた声かけ・接し方や子どもの自己肯定感を高める方法を紹介します。
子どもがすくすく成長していけるためのコミュニケーションのコツを紹介していくので、ぜひ最後までご覧ください。
子どもとのコミュニケーションの重要性

子どもとどのようなコミュニケーションを取るかは非常に重要です。
なぜならコミュニケーションが下記のように子どもの成長に影響を与えるからです。
- 自己肯定感の向上
- 信頼関係の構築
この項目では、上記2点について具体的にどのような声かけが効果的か紹介します。
今現在子どもとのコミュニケーションについて悩んでいるママやパパはぜひ参考にしてください。
コミュニケーションが子どもの成長に与える影響
子どもとのコミュニケーションは、信頼関係の構築や自己肯定感の向上に大きな影響を与えます。
というのも、親子間の良好なコミュニケーションは子どもが安心感を持ち、自分自身を肯定的に捉える土台となるからです。
例えば、日常的に「〇〇ちゃん(くん)はなんでそう思うの?」といった声掛けをすることで、子どもは自分の考えが尊重されていると感じ、自己肯定感が高まります。
しかし、急いでいる場面だとつい「そのやり方だとダメだからママ(パパ)のいう通りにやってごらん」という声かけをしていませんか?
このような声かけは子どもにとって、自分のやり方や考えはママやパパに信じてもらえないと感じ、自己肯定感が下がってしまいます。
そのため、「すごくいいね!こうするともっと上手くいくかもしれないよ。一緒にやってみようか!」のようなポジティブな言い方に変更してあげると、子どもの自己肯定感があがります。
また、コミュニケーションを通じて子どもは社会的スキルを学ぶことができます。
ママ・パパが子どもの話をしっかりと聞き、共感を示すことで、子どもは他者との関わり方を学びます。
これにより、子どもは自信を持って他者とコミュニケーションを取ることができるようになります。
子どもの発達段階にあわせた接し方

この項目では、子どもの発達段階にあわせた接し方を以下のようにまとめました。
- 乳幼児(生まれてから1歳になるまで):安心感と信頼感を育む接し方
- 1~3歳:自立性を育てるための接し方
- 4~6歳:自発性を促すための接し方
また、1~3歳の項目ではイヤイヤ期の接し方を紹介します。
子どもの年齢にあわせたコミュニケーションを取ることで、先述した信頼関係の構築や自己肯定感の向上により良い影響が期待できるでしょう。
乳幼児(生まれてから1歳になるまで):安心感と信頼感を育む接し方
乳幼児期には、安心感と信頼感を育むことが最も重要です。
この時期の子どもは、ママやパパの愛情と保護を強く求めるからです。
声かけをするときは以下の3つのポイントを意識しましょう。
- 声を少し高めにする
- ゆっくり話す
- 抑揚をつける
上記を意識した言葉をかけることで、子どもは自分が愛されていると感じ、安心感が育まれます。
特に、高めの声で話してあげるのがポイント。
赤ちゃんは一般的に低い声よりも高い声に反応しやすいです。
また、言葉を理解できないことも多いので、言葉以外のコミュニケーションも重要になってくるでしょう。
例えば、抱っこやスキンシップは、赤ちゃんに安心感や信頼感を与えることができます。
また、泣いたときにはすぐに対応し、赤ちゃんが安心できる環境を整えることが信頼感の構築につながります。
1~3歳:自立性を育てるための接し方、イヤイヤ期の接し方
1~3歳の子どもは、自立性を育てるための接し方が求められます。
ポイントは共感を生むようなコミュニケーションをとることです。
例えば、下記のような命令口調の言葉や語尾が強い声かけは控えたほうが良いでしょう。
| 良くない例 | 言い換え例 |
| それはダメだから、ママ(パパ)がやってあげるね。 | すごくいいね!もっとこうしてみたらどうかな! |
| お片付けしなさい! | 一緒にお片付けゲームをしようね! |
また、この時期は「イヤイヤ期」とも呼ばれ、自分の意思を強く主張するようになります。
ママやパパは子どもの自立を尊重しつつ、適切なサポートを提供することが重要です。
例えば、「〇〇ちゃん(くん)、自分でやってみようか!」と励ましながら、必要なときには手助けをすることで、子どもは自信を持って挑戦することができます。
イヤイヤ期の効果的な接し方は以下の3つが挙げられます。
- 子どもの気持ちを理解する
- 共感を示す
- 「自分でやりたい」ことに対して共感する
そのため「それはダメだよ!」と言うよりも「そうだね、嫌だよね」「わかるよ、嫌だよね。でも一緒にやってみない?」と共感の言葉をかけることで、子どもは自分の感情が理解されていると感じ、落ち着きを取り戻します。
4~6歳:自発性を促すための接し方、自ら選ぶ機会を増やすなど
4~6歳の子どもには、自発性を促す接し方が求められます。
ポイントは、子ども自身に「選ばせてあげる」ようなコミュニケーションをとることです。
この時期の子どもは、自分で考え、行動する力を育てることが重要です。
ママやパパは子どもに選択肢を与え、自ら選ぶ機会を増やすことで、自発性を育むことができます。
例えば、「お洋服はママ(パパ)が選ぶね!」というより「今日はどの服を着たい?」といった質問をすることで、子どもは自分で決定する経験を積むことができます。
| 良くない例 | 言い換え例 |
| ここに座りなさい。 | どこに座りたい?〇〇ちゃん(くん)選んでみて! |
| 今日はこの遊びをしようか! | 今日はどんな遊びがしたい? |
| お野菜を食べなさい。 | 野菜を食べると可愛く(かっこよく)なるけど、〇〇ちゃん(くん)はどうする? |
自分で選んだということ・ママやパパが自分の意見を信じてくれたということは、自己肯定感の向上につながります。
また、子どもが自分の意見を表現する機会を増やすことも重要です。
ママやパパは子どもの意見を尊重し、「どう思う?」と問いかけることで、子どもは自分の考えを持つことができるようになるでしょう。
子どもの自己肯定感を高める方法

子どもの自己肯定感を高める方法は以下の2つの方法があります。
- ポジティブな声かけ
- 子どもの意思を尊重する接し方
この項目では具体的なポジティブな声かけの例を紹介しているので、ぜひ実践してみてください。
子どもの自己肯定感が高まると、何でも積極的に取り組むようになっていきます。
また、自分を大切に思うようになり、他人にも思いやりを持って接することができるでしょう。
ポジティブな声掛けの具体例
子どもの自己肯定感を高めるためには、ポジティブな声かけ、前向きに取り組めるような声かけが効果的です。
例えば、「よくがんばったね」「〇〇ちゃん(くん)ならできるよ」といった言葉は、子どもに自信を与え、挑戦する意欲を引き出します。
また、下記にポジティブな声かけ、前向きに取り組めるような声かけの一例を紹介します。
| 良くない例 | 言い換え例 |
| お水こぼさないの! | こうやって持つとお水こぼれないよ! |
| 危ないからウロウロしないで! | 危ないから手をつなごうね! |
さらに、「ありがとう」「すごくうれしい!」と感謝の気持ちを伝えることで、子どもは自分が役立っていると感じ、自己肯定感が高まります。
この時他人と比べる発言をしてしまうと、必要以上に競争心を持たせたり、他人を見下すようになってしまうので、伝え方には気を付けましょう。
| 良くない例 | 言い換え例 |
| 〇〇くんより足が速くてかっこいい | 足が速くてかっこいいね!すごい! |
| 〇〇ちゃんは挨拶してたよ! | 挨拶できるとママ(パパ)も嬉しい! |
また、具体的な行動を褒めることも重要です。
「今日はお片付けが上手にできたね!かっこいいね!」といった声かけは有効です。
子どもにとって分かりやすく、自分の行動が評価されていると感じることができます。
子どもが前向きに取り組んでくれるように伝えることが重要なので、例えば「昨日よりも『こんにちは』が大きな声で言えてたね!」といった褒め方でも大丈夫です。
子どもの肯定的な行動をいつも探すように心掛けるとよいでしょう。
子どもの意思を尊重する接し方
子どもの意思を尊重する接し方は、自己肯定感を育むために欠かせません。
親は子どもの意見や感情を尊重し、命令に近いような言葉を使わないことで、子どもは自分の考えや感情が大切にされていると感じます。
| 良くない例 | 言い換え例 |
| もう寝るよ! | もう寝る時間だけど、どうする? |
| 歯磨きの時間だよ! | 歯磨きしないとばい菌だらけになっちゃうけど、〇〇ちゃん(くん)どうする? |
親は子どもに選択肢を与え、自分で選ぶ機会を提供することで、子どもは自信を持って行動できるようになります。
日常生活での実践方法
この項目では、日常生活での子どもとの接し方の実践方法を以下の2つにまとめました。
- 効果的なコミュニケーションの取り方
- 子どもの感情に寄り添う具体的な方法
子どもの話を聞くというのは重要ですが、親の感情を子どもに伝えることも大切です。
これにより子どもの共感する力を育てることができます。
効果的なコミュニケーションの取り方
日常生活で効果的なコミュニケーションを取るためには、ママやパパが積極的に子どもの話を聞く姿勢を持つことが重要です。
例えば、子どもが話しかけてきたときには、目を見て話を聞き、共感の言葉をかけることで、子どもは自分の話が大切にされていると感じます。
また、ママやパパが自分の感情や考えを率直に伝えることも大切です。
「今日は疲れているから少し休ませてね」といった自己開示をすることで、子どもは親の気持ちを理解し、共感する力を育むことができます。
子どもの感情に寄り添う具体的な方法
子どもの感情に寄り添うためには、ママやパパが子どもの感情を理解し、共感を示すことが重要です。
例えば、子どもが悲しんでいるときには、「悲しいね、どうしたの?」と声をかけることで、子どもは自分の感情が理解されていると感じます。
さらに、子どもが感情を表現する機会を増やすことも大切です。
子どもに「今日はどんな気持ちだった?」と問いかけることで、子どもは自分の感情を言葉にする練習をすることができます。
ママ・パパが控えたほうがよい行動とその理由

ママやパパが控えたほうがよい行動は以下のようなものがあります。
- 否定的な言葉
- 無視
- 過度な干渉
ここでは、上記のような行動を控えたほうがいい理由を解説します。
親としての責任や子育てに対する不安から、つい子どもに干渉しすぎてしまうこともあるでしょう。
しかし子どもにとっては成長の機会を失うことになります。
否定的な言葉、無視や過度な干渉を避けたほうが良い理由
否定的な言葉や無視、過度な干渉を避けたほうが良い理由は、子どもの自己肯定感を低下させる原因となるからです。
例えば、「なんでできないの?」といった否定的な言葉は、子どもに自信を失わせる可能性があります。
代わりに、「次はどうすればうまくいくかな?」といった言葉をかけることが重要です。
また、子どもを無視することは、子どもにとって非常に傷つく行為となります。
ママやパパが子どもの話を聞かないと、子どもは自分の存在が無視されていると感じ、自己肯定感が低下します。しっかり話を聞いてあげて、傾聴の姿勢を見せましょう。
さらに、過度な干渉も避けましょう。
子どもが自分で考え、行動する機会を奪うことは、子どもの自立心を阻害することにつながります。子どもに選択肢を与えながら「自分で考えて自分で行動する」機会を作っていきましょう。
子どもが活き活きと輝く声掛けをしていこう
子どもが活き活きと輝くためには、親子で楽しくコミュニケーションを取ることが重要です。
ママやパパは子どもの話をしっかりと聞き、共感を示すことで、子どもは自分の感情や考えが尊重されていると感じます。
また、ママやパパがポジティブな声掛けをすることで、子どもは自信を持って成長することができます。
「よく頑張ったね」「〇〇ちゃん(くん)ならできるよ」といった言葉は、子どもにとって大きな励みとなります。
親子で楽しくコミュニケーションを取りながら、子どもの成長をサポートしましょう。
ちょっとした声かけの工夫で、自己肯定感を高めることができ、
将来自分で考えて自分で行動できるようになります。ぜひ実践していきましょう。