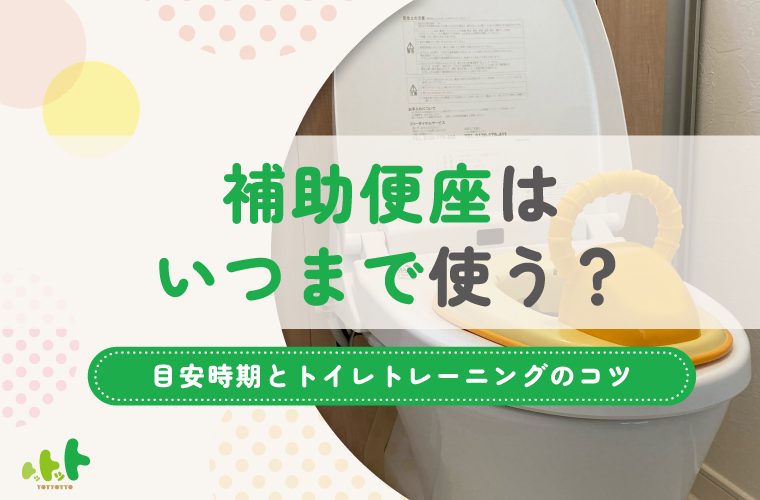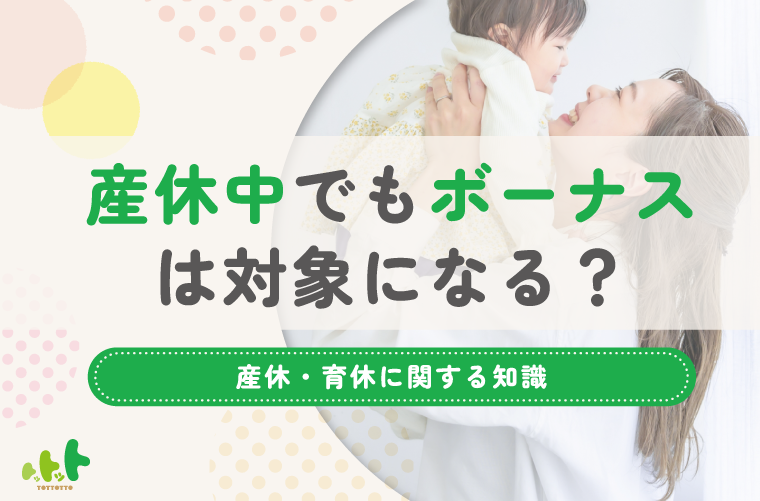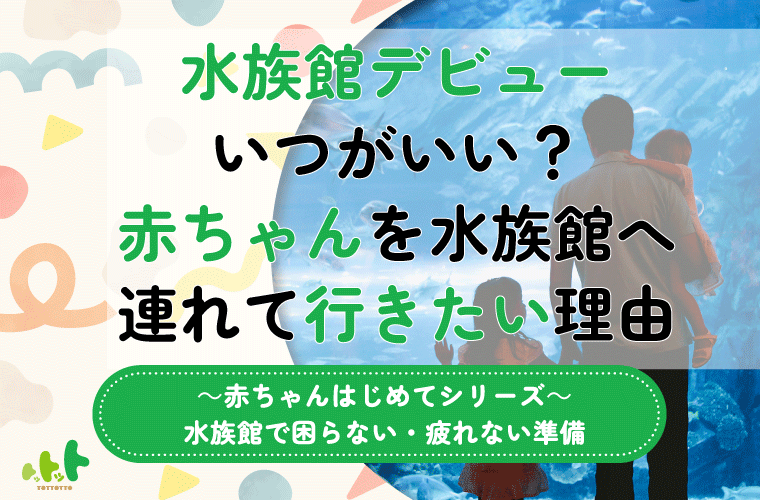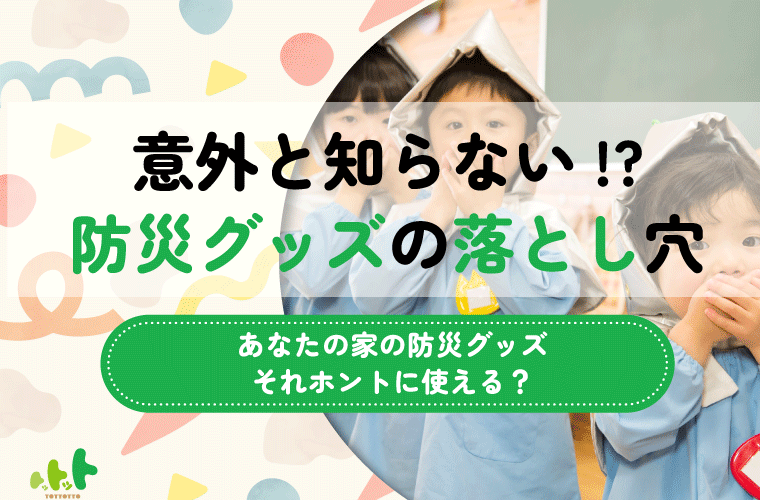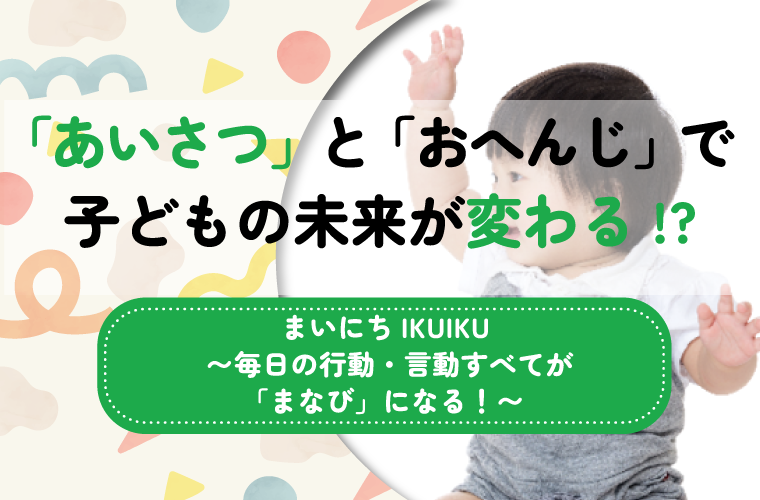赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て

子どもが自ら進んでお片付けをするようになるには、どんな声掛けが有効なのでしょうか。
「片付けなさい」と言っても、子どもはその意味を理解しにくいことがあります。
そこで、発達段階に合わせた声掛けをおこない、楽しい雰囲気を作ることで、子どもが自発的にお片付けするように促すことができます。
この記事では、子どもがお片付けの習慣を身につけるための声掛けのコツと、楽しみながら片付けを進める方法を紹介します。
お片付けの習慣をつける重要性
まず、お片付けをすることで、自分の持ち物を管理する力が育ちます。物を整理することで、何が必要で何がいらないのかを理解できるようになります。これは、物の大切さを知るための第一歩です。
次に、お片付けをすることで物を大事にする気持ちや責任感が育まれます。自分が使ったものは自分で片付ける習慣を身につけることで、子どもは自分の行動に対して責任を感じるようになります。
また、お片付けは周りの人に対する配慮も学ぶ機会です。自分の持ち物を整えることで、家族や友達と共有するスペースを大切にすることができます。これにより、他の人との関わり方も学び、社会性が育まれます。
日常生活の中でお片付けを楽しみながら習慣にすることで、子どもは自信を持って自己管理ができるようになります。
子どもがお片付けを苦手とする理由

お片付けはさまざまな要素が絡み合った複雑な行動です。多くの子どもは、片付けを苦手と感じることがありますが、その背景にはいくつかの理由があります。
具体的に、どのような理由があるのか、考えてみましょう。
自分で何をどう片付けるのか判断が難しい
たとえば、おもちゃがたくさんある場合、子どもはそれぞれの種類や形に基づいて分類することが難しいかもしれません。大人は「ブロックはここ、ぬいぐるみはあそこ」と具体的に分けられますが、子どもはそれを理解するのに時間がかかります。
物事を整理したり、計画を立てたりする力がまだ十分に育っていない子どもには、片付けるという作業が複雑で面倒に思えてしまうことが多いのです。
集中力や興味の持続時間の短さ
子どもは、大人に比べて集中できる時間や興味を持続させる時間が短いです。
これは、まだ脳が発達途中で、注意をコントロールする力が弱いためです。
子どもは新しいものに興味を持ちやすく、遊んでいるときもすぐに別のことに目が向いてしまいます。また、周りの音や動きに敏感で、刺激が多い環境では集中しにくくなります。さらに、体力が限られているため、長い時間活動するのが難しいこともあります。
お片付けは楽しくないという気持ち
子どもは遊びに夢中になっているため、楽しい遊びを中断して片付けをすることに抵抗を感じます。
また、子どもにとっては遊び道具も特別なものなので、片付けることが遊びの終了を意味する場合があります。これにより、片付けを避けたり、嫌がったりすることがあります。
発達段階に合わせた声がけのコツ

子どもがお片付けを苦手とする理由を理解した上で、適切な声がけを行うことが大切です。子どもがやる気を持って片付けに取り組めるようにするためのコツを紹介します。楽しく、効果的な声がけを通じて、子どもの片付けの習慣づけをサポートしましょう。
乳児期
この時期の子どもは、まだ片付けをするという概念がありません。遊びに夢中になり、物を散らかすことが日常です。声がけとしては、「おもちゃを一緒にしまおうね」「これを元の場所に戻してみよう」といった簡単で具体的な指示が効果的です。また、楽しい雰囲気を作り、一緒に遊びながら片付けることを楽しむことが重要です。
幼児期
幼児期になると、子どもは少しずつ物の整理や片付けを理解し始めますが、まだまだ難しく感じることがあります。この段階では、具体的な声がけを用いて「このおもちゃはこの箱に入れよう」「次はこの本を本棚に戻そう」と指示することが有効です。また、片付けを終えた後には、「よく頑張ったね!」と褒めてあげることで、自己肯定感を高めることができます。
学童期
学童期になると、子どもは自分で考えて行動する力がついてきます。しかし、忙しい学校生活や友達との遊びに気を取られて、片付けを後回しにしがちです。この段階では、「片付けの時間を決めて、一緒にやってみよう」「自分の部屋を整理するのは大事だよ」といった声がけが効果的です。また、片付けの理由や重要性を説明し、子ども自身が片付けに対する意識を持てるようにサポートすることが重要です。
楽しい雰囲気づくりの工夫

楽しい雰囲気を作り一緒に遊びながら片付けるためには、以下の具体的な方法を試してみると良いでしょう。
ゲーム感覚で片付ける
片付けをゲームに変えてみましょう。例えば、「おもちゃを何個早く片付けられるか競争しよう!」や「このおもちゃを何秒以内に元の場所に戻せるか試してみよう」といったルールを作ることで、子どもが楽しんで参加できるようになります。
音楽をかける
明るい音楽を流しながら片付けをすることで、楽しい雰囲気を作り出せます。音楽に合わせて片付けをしたり、リズムに乗って動くことで、片付けがより楽しいアクティビティに変わります。
テーマを設定する
例えば、「スーパーヒーローになっておもちゃを片付けよう!」というテーマを設け、子どもに役割を与えると、楽しんで片付けに取り組むことができます。スーパーヒーローのように素早く片付けを終えようとする姿が見られるかもしれません。
達成感を与える
片付けが終わったら、「見て、こんなにきれいになったね!」と達成感を感じられるように声をかけましょう。ご褒美としてシールを貼るなど、成果を見える形で示すことで、次回も頑張ろうという意欲が生まれます。
一緒に片付ける
子どもと一緒に片付けることで、遊びながらのコミュニケーションが生まれます。「これ、好きなおもちゃだね」「このおもちゃはどこに戻そうか?」と会話をしながら行うことで、楽しさが増します。
お気に入りの道具を使う
子どもが好きなキャラクターの箱やカラフルな収納ボックスを用意すると、片付けること自体が楽しくなります。お気に入りの道具を使うことで、子どもが自発的に片付けをしたくなることがあります。
これらの方法を通じて、子どもが片付けを楽しめるように工夫し、自然とお片付けの習慣を身につける手助けをしてあげましょう。
お片付けの習慣づけの方法
お片付けを習慣化するためには、いくつかのコツがあります。
まずは「お手本を見せながら一緒に片付ける」ことが大切です。ママ・パパが片付けの手順を見せることで、子どもはどのように片付けるのかを理解しやすくなります。例えば、一緒におもちゃを片付ける際に、どの箱に何を入れるかを具体的に示してあげましょう。
次に「片付けるタイミングを決める」ことも効果的です。毎日同じ時間に片付けをすることで、ルーティンができ、子どもも自然とその時間に片付けを意識するようになります。たとえば、寝る前に「そろそろお片付けの時間だよ」と声をかけることで、片付けの習慣が根付きます。
最後に、子どもが片付けられたら「たくさんほめる」ことが重要です。成功体験を重ねることで、自信を持って次回も片付けに取り組むことができるようになります。例えば、「おもちゃを上手に片付けられたね!すごいよ!」と具体的にほめてあげると、子どもはさらにやる気を出すでしょう。
これらのコツを取り入れることで、楽しく効果的にお片付けを習慣づけることができるようになります。
よくある質問
どのくらいの頻度で片付けをするべきですか?
毎日、決まった時間に片付けをすることが理想です。寝る前や遊びの後など、日常のルーティンに組み込むことで習慣化しやすくなります。
片付けをさせるための収納方法は?
色や形がわかるように収納箱を使い、見える場所におもちゃを整理することがポイントです。また、ラベルを貼ることで、どこに何をしまうかがわかりやすくなります。
お片付けの声がけまとめ
お片付けは子どもにとって面倒に感じられる作業ですが、適切な声がけをすることで、その習慣を楽しく身につけることができます。
子どもはまだ成長過程にあり、理解力や自立心が育まれる段階にあります。
楽しい雰囲気を作りながら、子どもが自分から片付けをしたくなるようなアプローチを一緒に実践していきましょう。