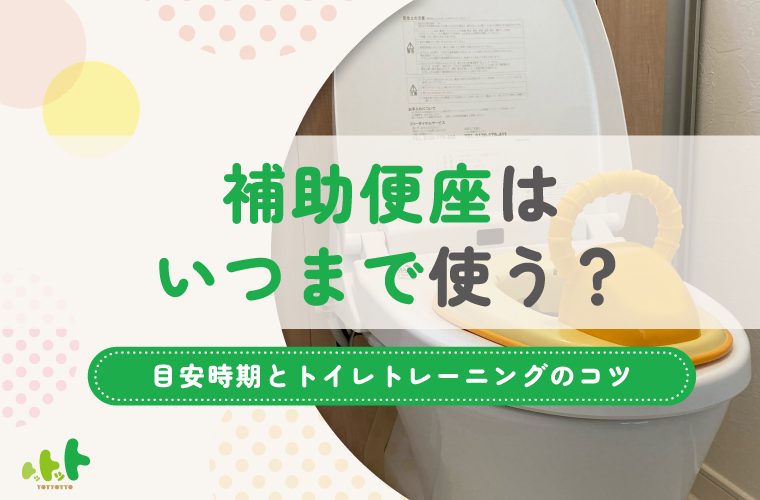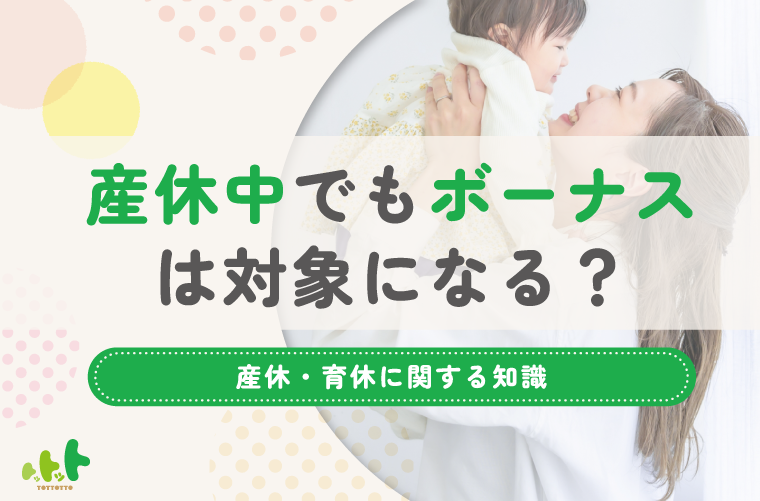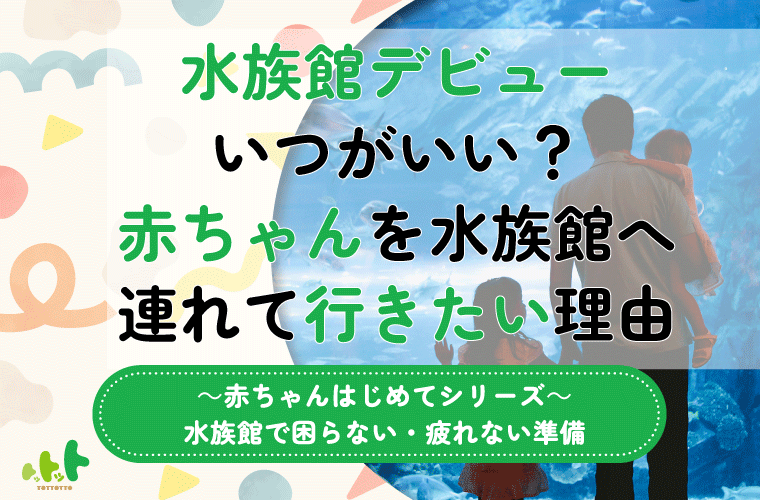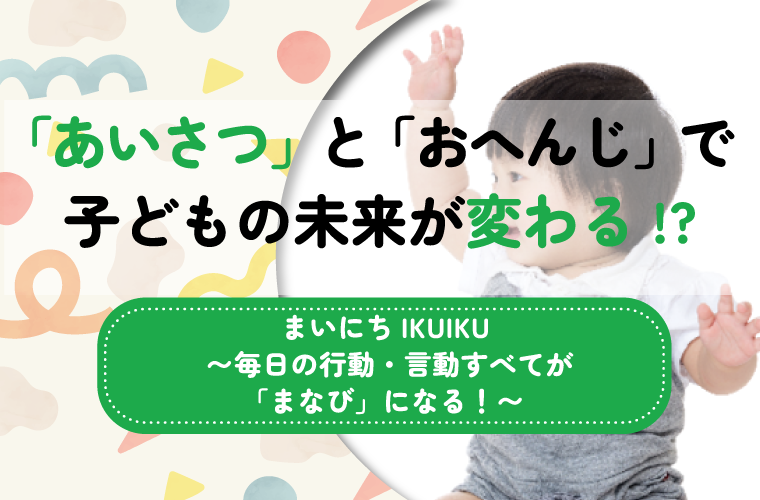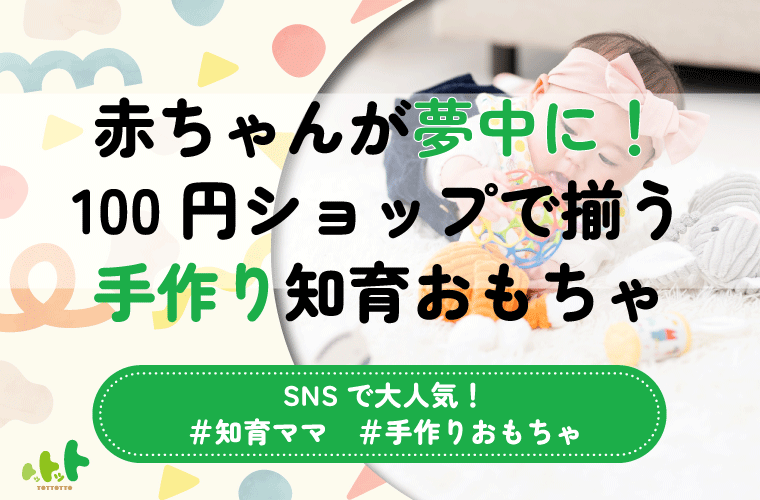赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て

ママやパパにとって、感染症やインフルエンザ対策はとっても気になりますね。
今回は、手洗いや消毒、換気などの基本対策から、家庭内の環境衛生、食事と睡眠による免疫力アップの方法、季節ごとの対策ポイントまで、ご家庭でできる予防について詳しく解説します。
感染症のリスクを減らし、安心して初めての冬を乗り切るための参考にしていただけると嬉しいです。
子どもの感染症予防の重要性

特に、小さなの子どもを育てるママやパパにとって、初めての冬は感染症への対策をどのようにしたら良いか、心配なことも多いですね。
子どもに限らず、肌寒くなってくるシーズンは、インフルエンザや他の感染症にかかりやすい時期とされています。そのため、日常生活での予防対策をしっかりと行うことが必要です。まずは、家庭でできる基本的な予防策について詳しく見てみましょう。
感染症予防の基本対策
子どもの健康を守るためには、基本的な感染症予防がとても大事です。手洗いや消毒などのポイントを参考にして、安心して冬を迎える準備をしましょう。
手洗いの徹底
手洗いは感染症予防の基本中の基本です。外から帰ってきた時や食事前、トイレの後など、しっかりと20秒以上かけて石鹸と流水で手を洗う習慣をつけましょう。外から帰ったら、手を洗うことをルーティン化することで、手洗いの習慣が身につきます。
小さな子どもは、ひとりでの手洗いが難しいので、ママやパパが洗面所で手を洗ってあげましょう。水を嫌がってしまう子どもは、濡れたタオルで拭くことから始めて、ママ・パパと手洗いの歌を歌いながら、楽しく手洗いをすることで、徐々に水に慣れるようになります。
消毒のポイント
手洗いに加えて、手の消毒も効果的です。アルコール含有の手指消毒剤を使って、手洗いが難しい状況でも手指を清潔に保つように心がけましょう。
1歳前後は、何でも手掴みで口に持っていく時期のため、外出するときに、除菌シートや携帯用の除菌ジェルをバッグに入れておくと安心ですね。また、ドアノブやリモコン、スマートフォンなど、手が頻繁に触れる場所も定期的に消毒することで、感染のリスクを抑える効果が期待されます。
換気の重要性
室内の空気の循環を良くすることも感染症予防に役立ちます。
特に冬場は暖房を使うため換気が疎かになりがちですが、1日に数回は窓を開けて新鮮な空気を取り入れましょう。また、加湿器を使って湿度を保つことも効果的です。湿度が40〜60%に保たれていると、ウイルスの活動が抑えられると言われています。
家庭内の環境衛生
家庭内の衛生管理は、感染症予防にとても大切です。家具やおもちゃの掃除、咳やくしゃみのマナーなど、日常的に心がけるべきことを一緒に見てみましょう。家庭内の環境を清潔に保ち、子どもが安心して過ごせる空間を作るためのポイントを紹介します。
家具やおもちゃの衛生管理
家庭内の衛生状態を保つために、家具やおもちゃの定期的な掃除が必要です。特に子どもがハイハイする場合は、気になってしまいますね。掃除機だけでなく、ウイルスが付着しやすい場所を重点的に定期的に拭き掃除をして、遊ぶスペースは清潔に保つことをすること心がけましょう。
ウイルス拡散を防ぐ習慣
乳幼児は、マスクをすることが難しく、自分で咳やくしゃみをする時に口をしっかりと覆うこともできません。万が一、子どもに風邪症状がある場合は、ママ・パパに感染しないように気をつけましょう。
また、ウイルスによっては、飛沫だけではなく接触したことで感染する場合があります。可能な範囲でタオルや食器を家族で共有しないようにし、使った後はしっかりと洗って乾燥させることが大切です。これらの小さな習慣が、家庭内でのウイルス拡散を防ぐ効果があります。
食事と睡眠で免疫力アップ

バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけることで、健康を維持しやすくなり、免疫力を高める効果があると言われています。ここでは、食事と睡眠を通じて免疫力をアップさせるためのポイントを紹介します。
バランスの取れた食事
免疫力を高めるためには、栄養バランスの良い食事が不可欠です。野菜、果物、タンパク質をバランス良く取り入れた食事を心掛けましょう。特にビタミンCやビタミンDは免疫力をサポートする栄養素として知られており、これらを含む食材を積極的に取り入れましょう。
離乳食後期にぴったりなレシピを2つご紹介します。どちらも簡単に作ることができますので、ぜひ、お試し下さい。
※どちらのレシピも作りやすい分量です。子どもに合わせて食べさせる量を調節し、余ったものは冷凍するなどして、早めにお召し上がりください。
野菜と鶏肉のスープ
(材料)
鶏胸肉:50g
人参:1/4本
ほうれん草:少量
じゃがいも:1/4個
玉ねぎ:少量
水:200ml
少量の無添加のチキンブイヨン(塩分控えめ)
(作り方)
- 鍋に水を入れ、鶏胸肉、人参、じゃがいも、玉ねぎを入れ中火で煮ます。
- 具材が柔らかくなったら、ほうれん草とチキンブイヨンを加えてさらに煮ます。
- 全ての材料が柔らかくなったら、完成です。
フルーツヨーグルト
(材料)
バナナ:1/4本
リンゴ:1/8個
ヨーグルト:大さじ2(無糖)
ベビービスケット:1枚
(作り方)
- ボウルにカットしたバナナとリンゴを入れます。
- ヨーグルトを加え、よく混ぜます。
- 砕いたベビービスケットをトッピングしたら完成です。
※どちらのレシピも、子どもに合わせて具材の大きさを調整して下さい。
良質な睡眠
十分な睡眠も免疫力を高めるために重要です。1歳の子どもは多くの睡眠を必要とするため、規則正しい睡眠リズムを作り、十分な睡眠時間を確保しましょう。お昼寝の時間も大切にして、無理なくしっかりと休む習慣をつけることが必要です。
季節ごとの感染症対策ポイント
秋や冬にはインフルエンザが流行しやすく、春には花粉症対策が必要です。ここでは、季節ごとの具体的な対策ポイントをご紹介します。
秋や冬の対策
秋や冬はインフルエンザなどの感染症が流行する季節です。特に、外出時にはマスク着用を心がけ、人混みを避けるようにしましょう。また、帰宅後は手洗いと消毒を徹底し、感染を防ぎます。外出から帰ったらすぐに着替える習慣をつけることも効果的です。
春や秋の花粉症時期
花粉症の時期の外出時には花粉対策をしっかりと行い、帰宅後は顔や手を洗って花粉を払いましょう。空気清浄機を上手に使用し、室内の空気を滞留させない工夫を心がけることで、アレルゲン物質を少しでも減らす効果があります。
また、花粉の時期は、新生活のスタートの時期や、季節の変わり目ということもあり、免疫力が低下し、体調を崩しやすい時期とも言われています。喘息の発作や溶連菌感染症などの発症などにも気をつけたいですね。
子どもの感染症やインフルエンザ対策について、よくある質問

ママ・パパにとって、感染症やインフルエンザへの対策は不安や心配の種ですね。
特に、インフルエンザ予防接種の時期や手洗いと消毒の効果、外で遊んだ後の注意点について知りたいという声が多く寄せられます。
ここでは、みなさんのご質問に対して、詳しくお答えします。ぜひご参考になさって下さいね。
Q:インフルエンザ予防接種はいつ受けるべき?
インフルエンザの予防接種は、感染が流行する前の秋頃に受けるのが一般的です。子どもが初めて予防接種を受ける場合は、2回に分けて接種することが推奨されています。予防接種を受ける時期や回数については、かかりつけの医師に相談すると良いでしょう。
Q:手洗いと消毒、どちらが効果的?
手洗いと消毒はどちらも重要ですが、基本的には手洗いを優先しましょう。石鹸と流水で20秒以上かけて手を洗うことで、多くのウイルスや細菌を除去できます。手洗いができない状況では、アルコール消毒を併用すると効果的です。
Q:子どもが外で遊んだ後に気を付けることは?
外で遊んだ後は、すぐに手洗いを行いましょう。また、衣類や靴も定期的に清潔に保つことが大切です。おもちゃや道具も使用後はしっかりと消毒し、ウイルスの付着を防ぎましょう。帰宅後は、すぐに着替える習慣をつけることも有効的です。
Q:インフルエンザと他の感染症の違いは?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによって発症し、38℃以上の高熱や頭痛、関節痛、筋肉痛など、全身に強い症状が出るのが特徴です。また、インフルエンザ脳症や熱性けいれん、中耳炎といった合併症を引き起こしやすい点も、風邪とは異なります。
他の代表的な感染症としては、風邪(かぜ症候群)、RSウイルス感染症、ノロウイルス感染症があります。
風邪(かぜ症候群)は、鼻水や喉の痛みや軽い咳が主な症状です。
RSウイルス感染症は、発熱や鼻水など軽い症状が多いものの、重症化すると咳が悪化し、喘鳴や呼吸困難を引き起こし、細気管支炎や肺炎になることもあります。
ノロウイルス感染症は、胃腸に症状が出やすく、嘔吐や下痢が主な症状です。
家庭で実践できる感染症予防施策
家庭内での感染症予防には、基本的な衛生管理が大切です。
定期的な手洗いや消毒、室内の換気を徹底することで、ウイルスの拡散を防ぐとされており、また、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心掛けることで、子どもの免疫力を高める効果があると言われています。家庭全体で予防をして、健康な冬を過ごしましょう。
初めての冬を迎えるママ・パパにとって、これらの感染症予防策が少しでもお役に立てれば嬉しいです。感染症予防の知識を深め、家庭でできる対策を実践して、安心して子育てを楽しんでくださいね。