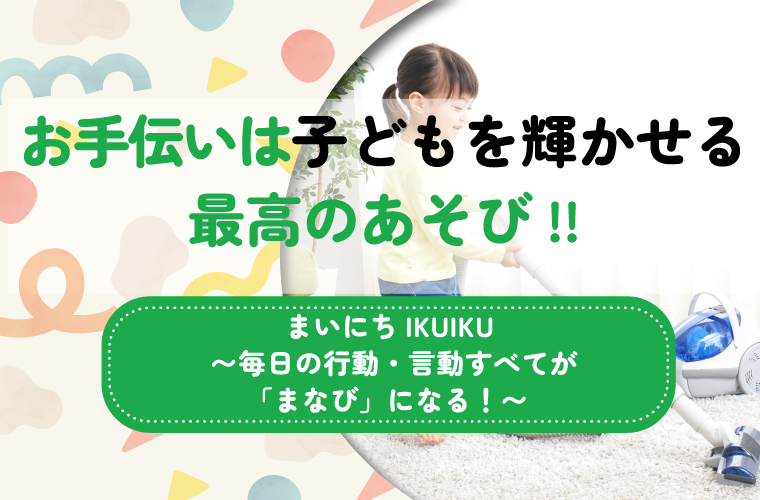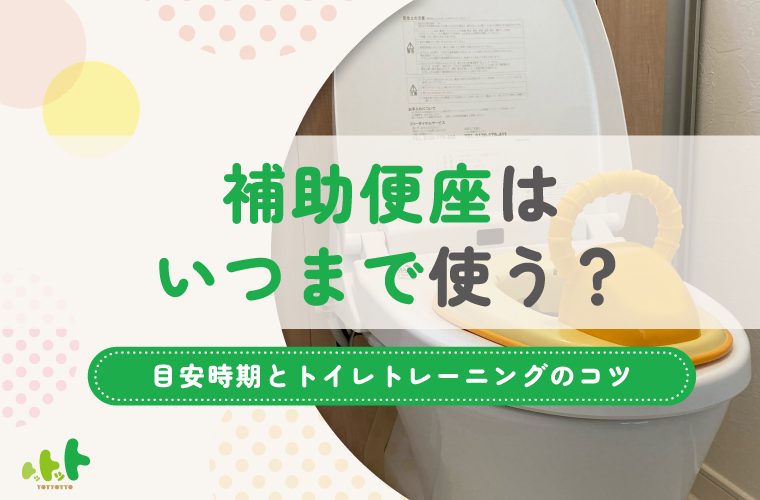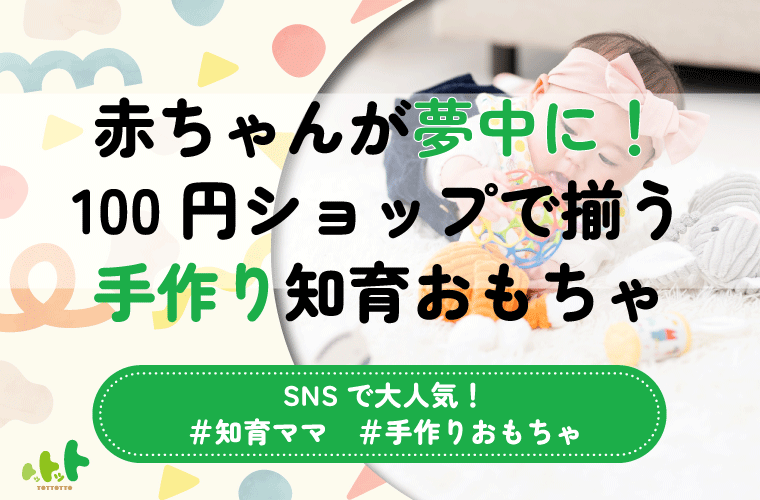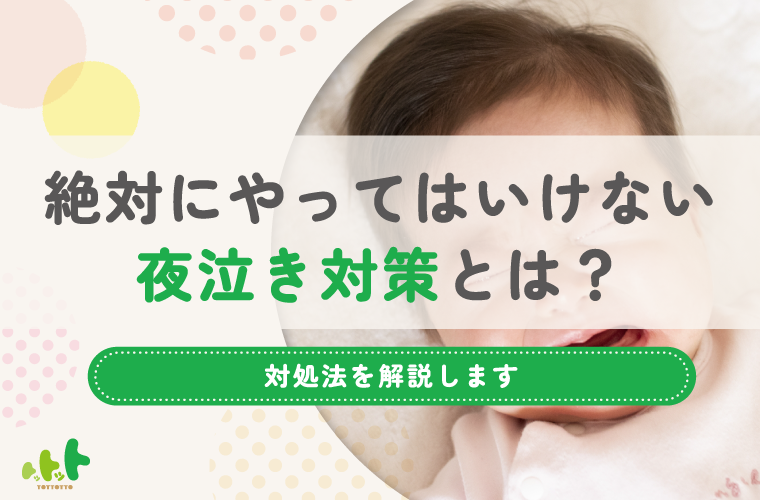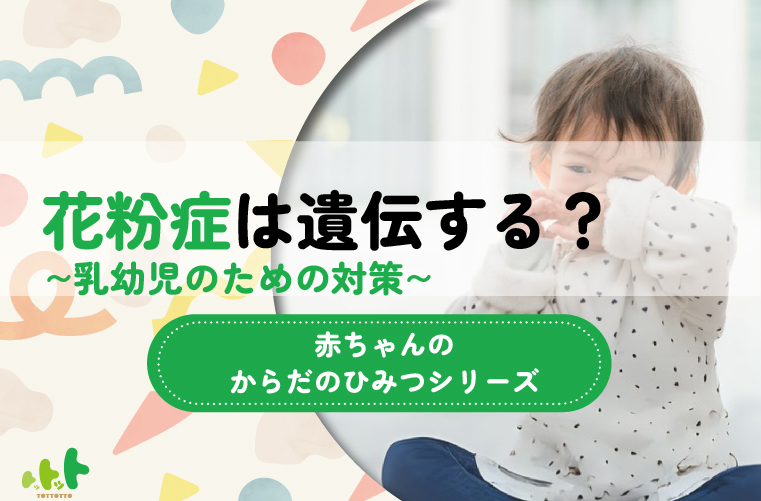マネー
マネー
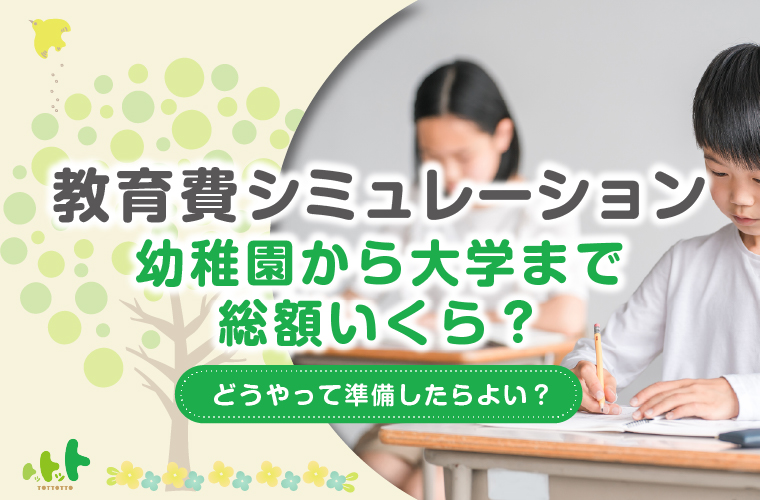
教育費は、一般的に子どもの成長とともに増えるものですが、幼稚園から大学まで一体いくら必要なのでしょうか。
大学までとなると、まだ先の話になりますが、子どもの教育費にだいたい総額でいくらかかるのか、把握しておくだけでも少し安心できますよね。
将来に必要なお金をコツコツ準備しておくきっかけにもなります。
この記事では、子どもの年齢や進学先にあわせた教育費を計算し、どうやって準備すべきかを解説します。
具体的には、解説する内容は以下の通りです。
- 幼稚園から大学までの教育費の平均
- 私立と公立での教育費の違い
- 無理のない家計で教育費を捻出する方法
- 教育資金の準備方法
- シミュレーション結果を活用して、家族の未来に対する計画を立てるコツ
ぜひ、この記事をきっかけに、子どもの未来を見据えた対策を始めてみてください。
幼稚園から大学までの教育費の平均

教育費は、幼稚園から大学まで、子ども一人当たりの総額が非常に大きな負担となります。
日本の平均教育費は、以下の通りです。
※教育費には学費以外にも交通費、教材費、塾や習い事の費用などが含まれます。
- 高校まで公立、大学のみ国立:約760万円
- すべて公立:約770万円
- 幼稚園及び大学は私立、他は公立:約1,120万円
- 小学校及び中学校は公立、他は私立:約1,280万円(私立)
- 小学校だけ公立:約1,530万円
- すべて私立:約2,230万円
(参考:文部科学省)
しかし、これらの金額は一般的な平均であり、具体的な教育費は地域や学校、家庭の事情によって異なります。
これらの費用を計算し、予算を立てることが大切です。
私立と公立の学費の違い
教育費における私立と公立の違いは、学費が大きな要素となります。
公立の学校は国や地方自治体が運営しており、学費が比較的安いです。
一方、私立の学校は独自の教育方針やカリキュラムを持ち、学費が高い傾向にあります。
具体的には、公立の高校の場合、年間約51万円の学費がかかりますが、私立高校では年間約105万円程度です。
大学においても、国立大学の学費は約242万円ですが、私立大学では所属する学部によって約400万~550万円と差があります。
(参考:文部科学省のデータをもとに算出)
教育方針や設備、教育内容にも違いがあり、公立・私立それぞれに特色があるため、進学先の選択には総合的な情報を収集し、子どもの将来や家庭の状況を考慮して決めることが重要です。
入学時と卒業時の費用を把握しよう
入学時には、大学や高校の学費だけでなく、準備や生活費も考慮する必要があります。
そのため、予算を立てる際には、入学金や授業料などの明確な金額だけでなく、教材費や交通費などの生活費も考慮する必要があることを、念頭においておきましょう。
どうやって多額の教育費を準備したらよい?
教育資金の準備方法を知ることは、子どもの将来のために非常に重要です。
教育資金の準備方法には、以下のものが存在します。

- 学資保険を利用する: 学資保険は、子どもの進学時に支払われる保険金で、教育資金の一部を補うことができます。
- 積立貯金定期預金や貯蓄口座を活用する: 毎月一定額を貯金することで、教育資金を蓄えることができます。
- 奨学金制度を活用する: 奨学金は、学費や生活費を支援するための無利子あるいは低利子の貸与で、教育資金の負担を軽減することができます。
- ただし、成績や家庭環境によって受けられる奨学金が異なるので、かならず活用できるものではない点は留意しておいてください。
これらの方法を組み合わせて、教育資金の準備を行うことで、子どもの将来をサポートすることができます。
学資保険の活用ポイント
学資保険を活用する際のポイントは、以下のような項目があります。
・適切な保険会社を選ぶ: 保険会社の評判や商品内容を比較し、自分のニーズに合った会社を選択することが重要です。
- 将来の教育資金を見積もる: 子どもの進学にかかる費用を把握し、保険金額を適切に設定することが求められます。
- 保険料の負担を考慮する: 保険料の支払い方法や期間を検討し、家計に無理のない範囲で契約することが望ましいです。
- 保険の特約やオプションを活用する: 通院特約や死亡保障など、追加のオプションを利用して、家族の安心を確保することができます。
これらのポイントを押さえることで、学資保険を効果的に活用し、子どもの教育資金を確保することができます。
積立貯金の効果的な使い方
まずは教育費がどのぐらい必要なのか、必要費用をざっくりでもいいので把握しておくといいでしょう。これにより必要な積立額が明確になります。
積立貯金は、毎月一定額を積み立てていくことで、将来の教育費を準備する方法です。早めにはじめることで、月々の負担を軽くすることができます。
積立貯金のメリットは、保険料が学資保険に比べて安価な設定ができることです。積立額をあとから変更することもできるので、生活状況や目標の変化に応じて積立額を見直すことができます。
また、積立貯金は自由に解約することも可能です。
積立貯金のデメリットは、学資保険と比較すると、一般的に利率が低く、お金が増えにくいことがあげられます。
学資保険では、契約満了時に受け取る金額はあらかじめ決まっていますが、積立貯金は満期時の受取額が期待した金額に達していない可能性があります。
契約者に万が一のことがあった場合に備えた保証もありません。
学資保険、積立貯金それぞれの選択肢には良い面も悪い面もあります。家庭の状況や目的に応じてどちらがあっているのかを検討してみてください。
公立や国立を選択すれば教育費は安くなるが…
公立の幼稚園や小学校、中学校、高校への進学を選択することで、学校教育や授業料の負担を軽減できます。
加えて、国立大学や国公立大学への進学を選ぶことで、私立を選んだ時よりも学費をおさえることができます。
ただし、単純に「学費が安くなる」という理由だけで、子どもの進路を決めてしまうのではなく、利用できる補助制度をしっかり検討した上で、子どもの将来のことを考え、子どもの希望をしっかり聞きながら、どの学校に通わせるべきか、選ぶようにしましょう。
シミュレーション結果を活用しよう
教育費シミュレーションは、子どもの進学や家計にかかる費用を見積もる有益な方法です。
シミュレーション結果を活用することで、予算や貯蓄計画を立てやすくなります。
また、シミュレーション結果をもとに、家計の無駄遣いを見直し、必要な教育費に充てる予算を増やすことが可能です。
将来の子どもの教育環境を考慮し、シミュレーション結果を活用して計画を立てましょう。

たとえば、下記のような公的機関が提供しているシミュレーションを活用してみるのがおすすめです。
すでに生命保険に入っている場合は、その保険会社のライフプランナーに相談することをおすすめします。
ライフプランナーは、各家庭の状況に合わせて親切にアドバイスをしてもらえます。
保険の内容を見直したり、将来のお金の準備についても詳しく教えてくれたり、教育費がいつ、いくらぐらい必要なのかもシミュレーションしてもらうことができます。
教育費シミュレーションで家族の未来を描こう
教育シミュレーションを通じて、子どもの教育にかかる費用や家庭の負担を把握することができます。
また、適切な貯蓄や支出管理により、家族の資産を増やし、子どもの教育に必要な費用を充足させることができます。
教育費シミュレーションを活用して、将来の家族の幸せを築くための計画を立てましょう。
ただ、今この段階で、未来の計画を事細かく決める必要はありません。あくまで「子どもの教育にはお金がかかる」ということを念頭において、できる準備を進めたり、先を見越して子どもや家族とコミュニケーションをとっておくことが大切です。
本記事で紹介したシミュレーションを再掲しておきますので、ぜひご活用ください。