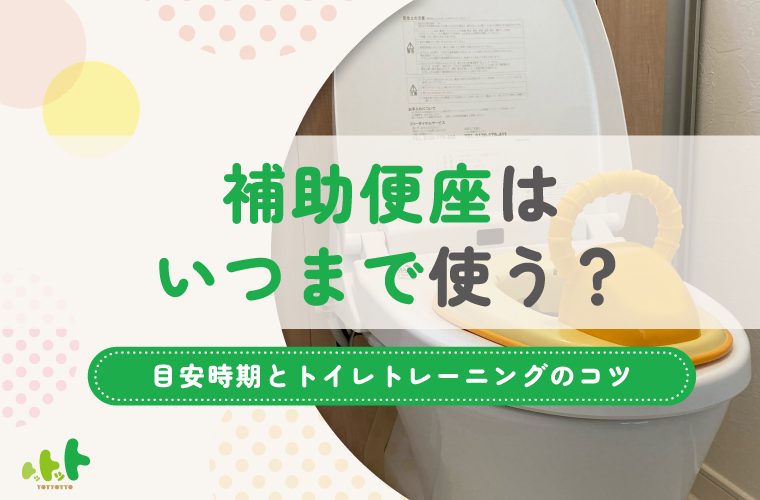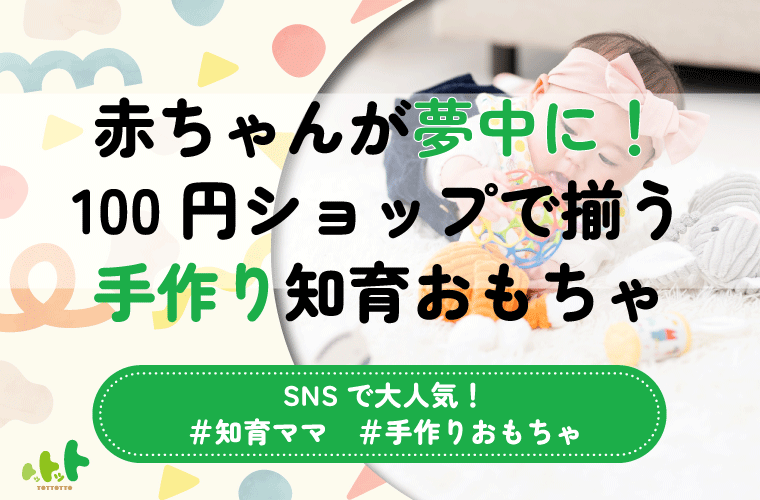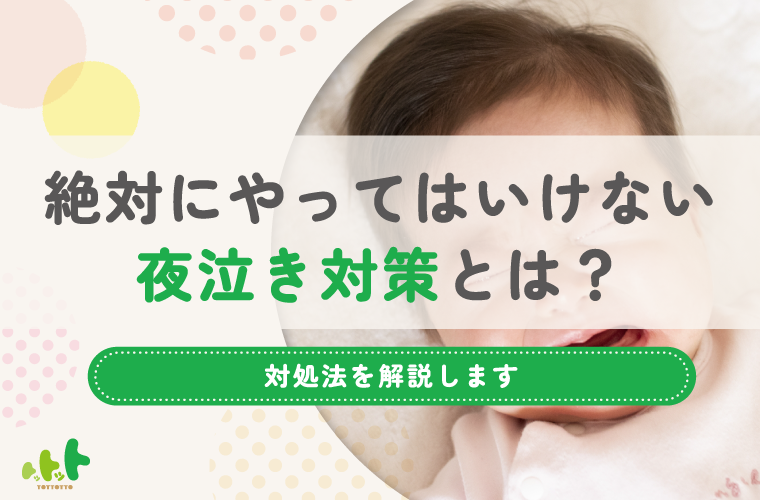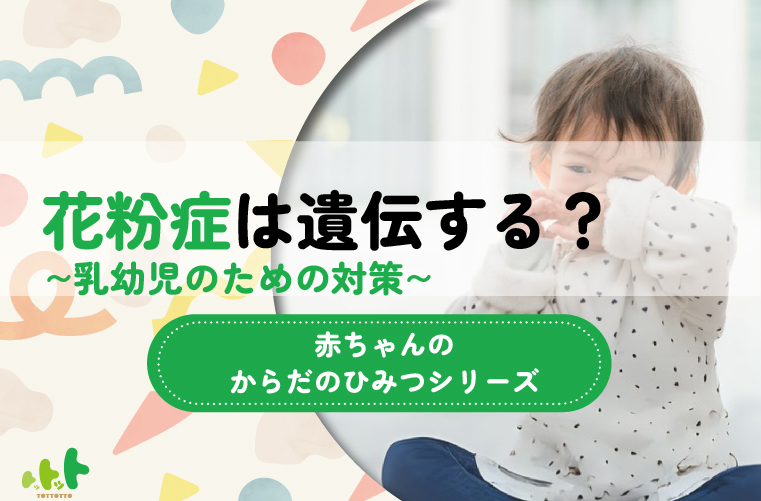赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て
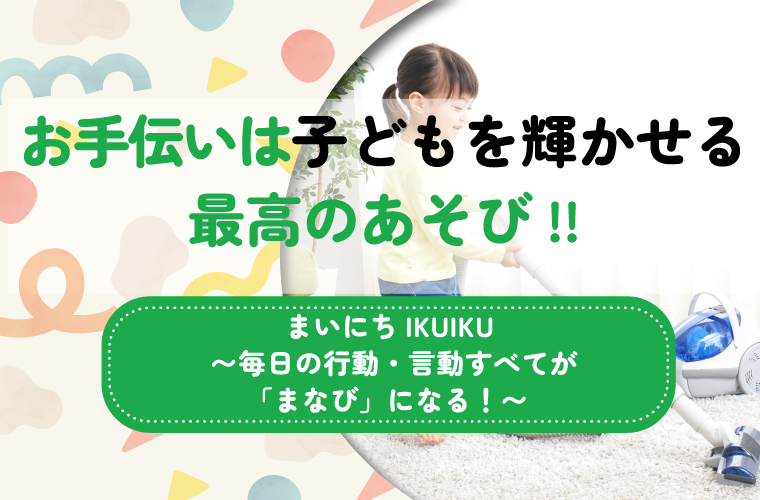
こんにちは、編集部Kです。
毎日の行動・言動すべてが「まなび」になる!毎日IKUIKU。今回のテーマは「お手伝い」をお届けします。
0歳から5歳くらいまでのお子さんが、社会やまわりのできごとを知り、理解する時にどこから学ぶかというと、それは、日常のできごとひとつひとつからです。
その中のひとつが「お手伝い」。
“お手伝い”は、お子さんの心やからだ、思考力などを大きく育ててくれる最高の「遊び」の一つです。
今回は、お手伝いが子どもの成長にどうかかわるのか、年齢別の具体的な例とともにご紹介します。
仕事と育児を両立しながらでも無理なく取り入れられるヒントを、ぜひチェックしてみてくださいね!
お手伝いは何歳からがいいの?

「3〜4歳くらいから少しずつ家事を体験させたい」という声が多い一方、0歳や1歳でもできることはあります。
海外の乳幼児教育では、歩き始めたら小さな袋を運ぶなど、一人ひとりの発達段階に合わせ、各家庭で「お手伝いあそび」を取り入れています。
子どもは“やってみたい!”の塊。
親がちょっと背中を押してあげるだけで、前向きに参加してくれますよ。
0歳〜3歳からの『おすすめお手伝い』
まだ、自分で動き回るのは難しい0歳児ですが、“体験の入り口”として「見せる・さわらせる」だけでも、お手伝いの土台づくりになります。
【0歳】 まずは「見て」「ふれる」だけでOK

1.“見学”というお手伝い
内容:
家事をするパパママを安全な場所から見てもらう。抱っこしながら動作を見せる、座ったまま動きを見せる…など
なぜ良い?:
「家事ってこんな感じなんだ」という興味を引き出し、将来のお手伝いへの「まねっこ欲」を育むきっかけになります
2.タオルを軽く握ってもらう
内容:
お風呂あがりや洗濯物を畳んでいるとき、小さなタオルやガーゼを「持っててね」とお願いする
なぜ良い?:
赤ちゃんが握る・さわるだけでも「参加している」という感覚が得られ、親子のコミュニケーションが深まります
3.ボタンを押す・スイッチを押す
内容:
洗濯機や掃除機などのスイッチを押すとき、赤ちゃんの指を誘導して一緒にプッシュする
なぜ良い?:
音や動きなど、押した後の変化がわかりやすく、“因果関係”への好奇心が刺激されます
4.テーブル上での受け渡し遊び
内容:
安全な小物を「ちょうだい」「どうぞ」で受け渡しするあそび
なぜ良い?:
「渡すと喜んでもらえる」というやり取りの感覚が、親子のコミュニケーションを深め、初歩的な社会性を育みます
【1歳】 できることが増え、まねっこが大好きになる時期

1.ゴミ箱にポイ
内容:
軽い紙くずやオムツ(袋入り)などをゴミ箱へ捨てる
なぜ良い?:
単純な動作でも「うまく入った!」という達成感が得られ、「役に立った!」という自信につながります
2.おもちゃの「どうぞ」「ちょうだい」
内容:
散らかったおもちゃを箱に片付ける際、「ちょうだい」「どうぞ」の言葉を交わしながら渡し合う
なぜ良い?:
遊びの延長で片付けが習慣づきやすく、親子のやり取りも増えるのでコミュニケーション力アップにもなります。
3.ブロックやおもちゃをふく
内容:
ウェットティッシュなどでブロックやおもちゃを拭く
なぜ良い?:
モノを大切に扱う気持ちや衛生観念に触れられ、自分の持ち物への愛着が育ちます。
4.軽いものを運ぶ
内容:
小さなぬいぐるみや紙パックなど「これ持ってきてくれる?」とお願いする
なぜ良い?:
子ども自身が“力仕事をした”気分になりやすく、自尊心や自立心をくすぐります。
【2歳】 まねごと上手! 自分でやりたい意欲がアップ

1.テーブル拭き
内容:
子ども用サイズの小さな布巾で「ここをクルクル拭いてみよう」と誘う
なぜ良い?:
手先が少しずつ器用になる時期で、“拭く”動作が発達にマッチ。遊び感覚で集中力も育ちます。
2.ハンガーにかける
内容:
パジャマやタオルなど軽い布類を、一緒にハンガーへかける
なぜ良い?:
まだ正確にかけられなくても、“服を扱う”家事動作の体験ができます。
3.野菜や果物を洗う
内容:
シンクで水を少し流し、大人のサポートのもと子どもがゴシゴシ洗う
なぜ良い?:
水遊び感覚で楽しめ、食べ物への関心も高まります。手先や水の感覚刺激が脳の発達にも◎。
4.洗濯物を手渡す
内容:
干す大人のそばで、洗濯物を1枚ずつ「はい、どうぞ」と渡す
なぜ良い?:
受け渡しの共同作業は「一緒にやっている」という連帯感が強まり、達成感も大きいでしょう。

【3歳】 集団生活が始まり、役割を楽しむようになる

1.食器運び・片付け
内容:
軽い食器をテーブルへ運ぶ、食後にシンクへ片付けるなど
なぜ良い?:
「家族の一員として役割を担う」喜びを感じ、“お手伝い=日常”という意識が芽生えます。
2.簡単な仕分け作業
内容:
靴下のペア探しや洗濯物の色柄分けなど
なぜ良い?:
パズルのように楽しめ、集中力や分類能力が育まれます。自分の物と他の人の物を区別する学びにもなります。
3.おやつや調味料の準備
内容:
お皿におやつを並べる、サラダにかけるドレッシングをテーブルへ置くなど
なぜ良い?:
簡単な料理サポートが「食べること」への関心を高め、家族を思いやる気持ちも育みます
4.玄関の靴をそろえる
内容:
帰宅後に乱雑になりがちな靴をそろえる“係”をお願いする
なぜ良い?:
“お世話役”として家族に役立つ体験ができ、マナーや整理整頓の意識が自然と身につきます。
ほかにもあるよ! 子どもがやりたがる楽しいお手伝い

- 水を使う洗いもの(食器洗いなど)
水遊び感覚が強く、小さな子どもに大人気! - 料理のサポート(かき混ぜ、卵割りの補助など)
おままごとの延長で、“できあがり”がわかりやすいので楽しみやすいです - 掃除機・モップがけ
“道具を操作する”冒険感があって子どもにウケます - 洗濯物を干す・運ぶ
体を動かすことで「力持ち気分」になれ、ママパパに喜ばれる感も高い! - 買い物カート押し・カゴ持ち
外の環境で活躍できるので、「役立っている!」と実感しやすいです
お手伝いのデメリットとは?

お手伝いをお願いしても、大人が思うようにはできないのが子ども。
わかっていても「今日はいまいち乗り気じゃない」「やろうとしたのに失敗しちゃった」ということは、当たり前のことです。
上手くいかない、続かない時は大人の知恵でいこう
時間がかかったり、失敗が増えたりしても、子どもの頑張りや発想を肯定するのが大人の役目。
とはいえ、家事や仕事で忙しいママパパだからこそ、イライラを溜めない工夫も必要です。
やる気が失せるのは日常茶飯事
今日はOKでも明日はダメ…なんてよくある話。波があると理解して、気長につき合おう!
進行が遅くなって時間がかかる
平日の忙しい時間より、まずは休日など時間に余裕のある日にゆったりトライしよう
小さな成功体験を作る
まずは、5分くらいでできるお手伝いからスタートすると、お子さんも「できた!」と達成感が得やすい
遊びとして盛り上げる
タイマーを使ったり、音楽をかけるなどして“イベント化”すると楽しく続けやすい
失敗や汚れが気になる…
われにくい食器や子どもサイズの掃除道具などで、安全対策を工夫する
できなくて、子どもが自信を失ったら…
「やってくれてありがとう」「ここまでは上手にできたね」とプラスの声かけをたっぷりかけて、ほめよう
試してみよう! 上手なお手伝いの誘い方&声かけ
「お手伝いさせたい」ではなく、「一緒に楽しもう!」と考えるだけで、子どものモチベーションもアップ。親子ともにストレスを減らしながら進めていきましょう。
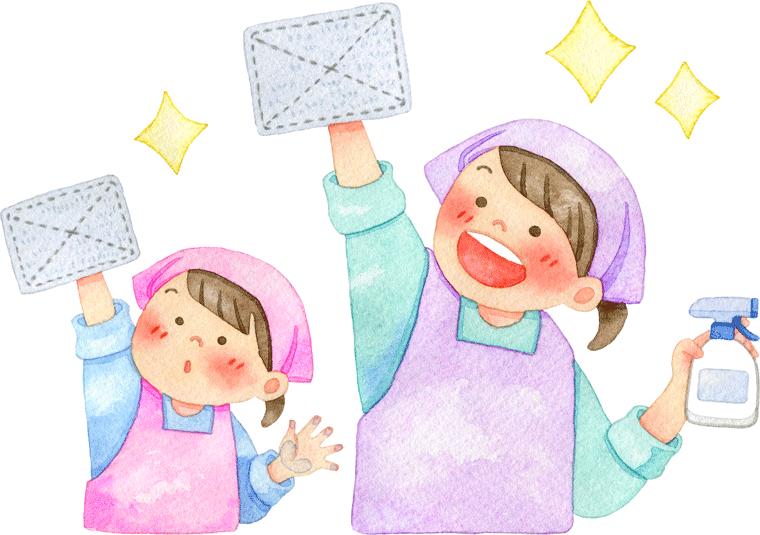
1.「一緒にやろう!」と巻き込む
「○○ちゃんと一緒にやると、ママ(パパ)は助かるな〜」と誘う。
子どもは“仲間感”を感じると喜んで参加し、自分が「必要とされている」ことに満足感をおぼえるでしょう。
2.「どっちがいい?」選択肢を与える
「洗濯物をたたむのと、机をふくの、どっちがいい?」と本人に選ばせる。
自分の意思で選んだという主体性がやる気を高め、「やらされている感」を減らせる。
3.失敗を前提にして、褒めポイントを見つける
「こぼれちゃったね。でも最後までやってくれたのがすごい!」とねぎらい+褒め言葉をセットで伝える。
プロセスを肯定すると、子どもは「次はもっと頑張ろう」と前向きになれます。

4.見通しを伝える
「テーブルを拭いてくれたら、もうすぐおやつにしよう!」と報酬や次のステップを提示。
先の楽しみがあるとモチベーションが上がり、集中力が続きやすくなります。
お手伝いで子どもが得る“すごいこと”
お手伝いは、子どもの「生きる力」を育む大切な体験といわれています。
とくに0歳から5歳までの小さな子どもが家族の手伝いをすることで、どんなメリットや変化が生まれるのかご紹介しましょう。

長期的な学力・社会性への影響も
家事分担を経験した子どもは、「自分で考えて動く力」が身につきやすく、将来の学校生活や社会での仕事にもプラスに働くと言われています。
段取り力・マネジメント力が身につく
「どの順番でやるとスムーズ?」「どう進めたらいい?」などを考えるうちに、自然と段取り力が鍛えられます。それはのちの仕事やプロジェクトにも役立つでしょう。
思いやりがあり優しい人に
「誰かのために」という気持ちと行動が、人への思いやりや協力する姿勢につながっていきます。
コミュニケーション力が身につく
家族と一緒に作業し、褒め合い助け合う経験を積むことで、人とかかわるときのスキルや自信が高まります。
自己肯定感とチャレンジ精神アップ
「自分は役に立てる存在なんだ」という実感は、成長とともに「もっとやってみよう!」という挑戦心に結びつきます。
まとめ:
「お手伝い育」で小さな成功体験を重ねよう
子どもは、日々のちょっとした体験から“生きる力”を育てていきます。
大事なのは、「子どものペースに合わせて失敗しても笑い合う」こと。時間はかかるかもしれませんが、「一緒にやると楽しいね」と肯定する言葉が、子どもの脳・心・体を伸ばすエネルギーになります。
仕事と育児を両立しているママパパにも負担にならない方法で、「お手伝い育」を始めてみませんか? その小さな成功体験は、15年後・20年後の大きな自信にきっとつながっていきます。
参考文献・資料
・文部科学省『幼児期の学びに関するガイドライン』
・厚生労働省「健やか親子21」
・ベネッセ教育総合研究所「幼児の家庭学習・お手伝いに関する調査」
・Nelson, J.K. (2019). “The Effects of Household Chores on Child Development,” Early Childhood Journal.
・Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2012). Child Development. McGraw-Hill.
・Steinberg, L. (2020). “Positive Child Development through Household Responsibilities,” Developmental Psychology Review.
・家政学学会誌『日本における家事育児の歴史と子ども観』
・発達心理学研究Vol.60「幼児の食育と家事連携」
・保育学研究所「幼児の外出行動に関する一考察」
・海外家庭教育関連資料(Montessori教育プログラム、アメリカ各州のChore Lists など)