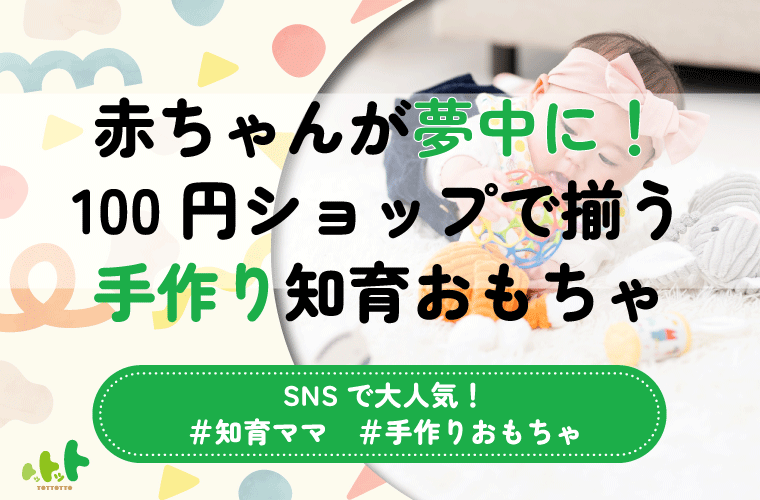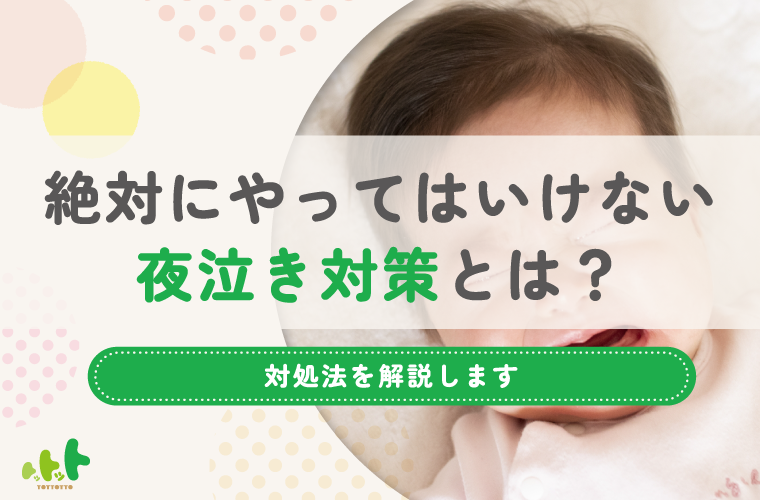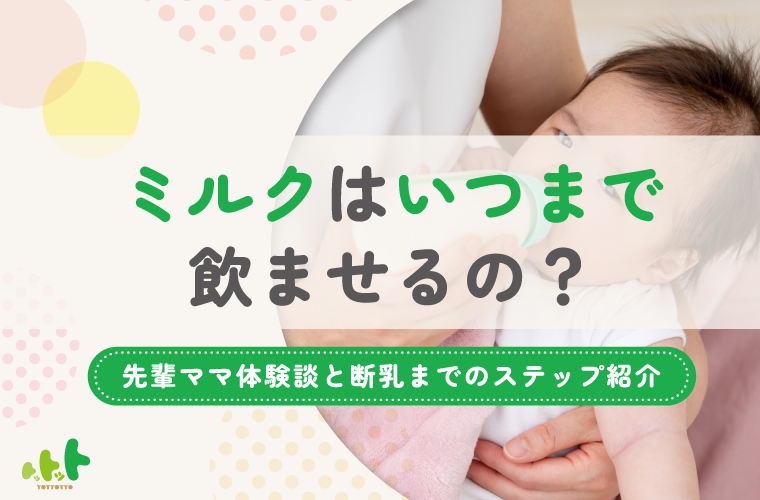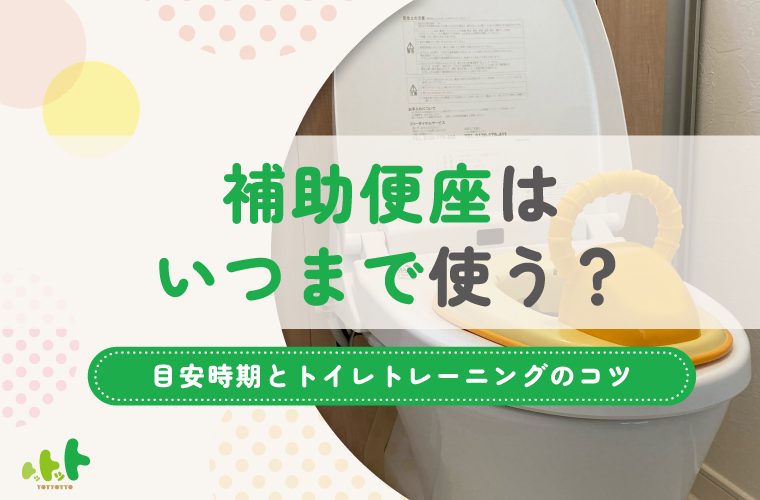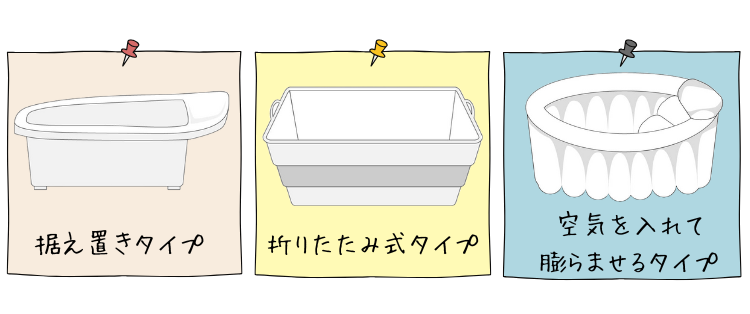赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て

離乳食を1日3回食べられるようになってくると、赤ちゃんのおやつについての情報を目にすることが増えますよね。
市販の離乳食売り場で「生後7ヵ月ごろからのおせんべい」などの表示に
「おやつはいつ頃からあげるのがいいのかな?」
「市販のお菓子もあげて大丈夫?」
「チョコレートやファストフードはいつから?」
とどんどん疑問がふくらんでくることでしょう。
管理栄養士の岡本正子先生に、安全に与えるための注意点を教えてもらいました。
子どものおやつ、いつからあげるのが正解?

「うちの子、そろそろおやつデビューかな?」
そう思ったママ&パパ、ちょっと待って!
おやつはただのおやつにあらず。子どもの成長をサポートする、大切な栄養タイムでもあるんです。
正しい知識を得て、お子さんの健康と成長をサポートしてあげてくださいね。
まずはおやつの役割について考えてみましょう!
おやつの役割って?
- 体の栄養チャージ:3回の食事じゃ足りない栄養を補給! 消化器官がまだまだ成長段階にあるお子さんは一度にたくさんの量を食べられないので、間食(おやつ)で栄養を補います。
- 心の栄養チャージ:甘いものを食べてほっとしたり、お菓子を囲んで楽しい時間を過ごしたり。子どもの心身のリフレッシュや、親子のコミュニケーションを深める役割も果たします。食事の練習にもつながります。
おやつは、子どもの成長に必要な栄養素を補給するだけでなく、食事の練習や、心身のリフレッシュ、親子のコミュニケーションを深める役割も担っています。
さらにおやつには、食事と同じように「生活リズムを整える」効果もあるんですよ。
ただし、与える時期や内容、量によっては、子どもの成長に悪影響を与える可能性も。
子どもの成長と発達に合わせた、安全なおやつタイムの過ごし方を詳しく見ていきましょう。
おやつデビューの目安は?

市販の離乳食売り場では、「離乳食中期(生後7〜8ヵ月)向けの赤ちゃん用せんべいやビスケット」などが販売されていることもあり、生後7〜8ヵ月ごろからおやつを取り入れている人もいます。
しかし、栄養面からいえば、補食が必要になってくるのは1歳ごろからです。
「おやつにしよう!」という言葉で、頭に浮かぶものはなんでしょうか?
甘いものから塩辛いものまで、人それぞれ思い浮かぶものが異なることでしょう。
でも、小さなお子さんのためには、お楽しみのお菓子類はほんの少量にとどめ、おやつ=補食と考えてあげるようにしてください。
補食と聞くとお楽しみがないように感じるかもしれませんが、フルーツやヨーグルトと考えれば立派なおやつになりますよね。
ですからおやつは、開始時期よりも「何を」「どれくらい」あげるかが重要なんです!
補食としてのおすすめおやつ例
1歳を過ぎて補食がはじまる時期は、まだ胃も小さいですし、1回の食事でたくさん食べられなかったり、ムラ食いをしたりすることがあります。補食で1日に必要な栄養をしっかり摂る必要があります。
おにぎりやパン類は代表的な補食ですが、ほかにも以下のようなものがおすすめです。
フルーツ

ビタミンの豊富なフルーツは、おやつとして最適。食事だけでは補えない栄養も摂取することができますよ。フルーツを使ったデザートはもちろんよいですが、フルーツをそのままいただくだけで子どもにとってはご馳走になりますから、ママ&パパの手間があまりかからない点でもおすすめです。
乳製品
乳製品アレルギーがないなら、ヨーグルトやチーズなどの乳製品をおやつに取り入れてみるのもおすすめです。成長に欠かせないカルシウムを補給できます。
一方で、同じ乳腺品でも非加熱のナチュラルチーズはNGです。小さな子どもにとっては塩分が多い傾向がありますし、キャンディーのような一口サイズの形状は誤えんしてしまうこともあるので、注意が必要です。
豆類
「豆類のおやつってどんなもの?」と一瞬想像がつかないかもしれませんが、例えばきなこの自然な甘味を利用したり、あずきを寒天で固めたりと、さまざまなバリエーションがあります。ただし、あんこなどは砂糖の量が多いので、2歳以降にしましょう。
おからを使った揚げ菓子「きらず揚げ」などもおすすめです。
野菜スティック

かむ力がついてきたお子さんなら、きゅうりや食べやすい固さに茹でたにんじんなどを野菜スティック状にしてあげてれば、ヘルシーなおやつに変身です!もちろんスティック状じゃなくとも、さつまいもなどの素材の甘味を感じられるいも類などもおすすめですよ。
さて、ここまでの例を見てお気づきでしょうか。
どれも素材本来の自然な甘味をいかしたおやつです。お子さんはママ&パパと比べて味覚が繊細で敏感です。素材本来のやさしい甘味でも十分なんです。
なかでも「干しいも」はイチオシです。かみごたえもありますし、シンプルです。ただし、粘り気もありのどにつまらせやすいので、こちらもかむ力、飲み込む力がそなわった2歳以降がいいでしょう。
とはいえ、この記事を読んくださっているママ&パパの中には、「手軽に用意できる市販のお菓子やファストフードを、どのように与えたらいいのだろう?」と疑問に思っている方もいるかもしれません。
市販のお菓子は、「選び方のコツ」をおさえておくことが大切ですよ。
お菓子デビューは慎重に! でも、たまにはご褒美もアリ?
市販のお菓子類は、味が濃いものや、糖質や脂質を多く含むものが少なくありません。
すると、お菓子を食べるとおなかがいっぱいになり、その後の食事が進まなくなってしまうことがあるので注意が必要です。
「食事をもりもり、しっかり食べているかな?」
「栄養バランスに偏りはないかな?」
といった点にも配慮しながら、心の栄養として少しずつ、上手にお菓子と付き合っていきましょう。
最低限押さえておきたい!市販のお菓子選び〜3つのポイント

お子さんに安全でおいしいおやつを選んであげるために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 原材料チェック!:添加物という名の小さな悪魔に注意!
- 砂糖&塩分チェック!:甘い誘惑、しょっぱい罠に気をつけて!
- 形状チェック!:喉に詰まる危険な形状はNG!
原材料チェック
食品を買うときに「原材料」をチェックしてみたことはありますか?
乳幼児のための食品選びには、ぜひ原材料チェックを習慣にしてみましょう。
特に、人工甘味料や着色料、保存料などの添加物が入っていないかを確認することが重要です。
【避けるべき原材料】
| 注意したい添加物の種類 | |
| 甘味料 | アスパルテーム、アセスルファムK、D-ソルビトール、サッカリンNa、スクラロースなど |
| 着色料 | 青1、赤2、黄4などのタール系色素、カラメル色素など |
| 保存料 | 安息香酸Na、しらこたん白、ソルビン酸Kなど |
また、アミノ酸も赤ちゃんには刺激が強いので避けたい添加物のひとつです。
赤ちゃん用の食品に使われていることはあまりありませんが、一般食品には使われていることが多いので、大人も食べるような市販のお菓子を与える際には注意が必要です。
※アレルギーをお持ちのお子様の場合は、アレルギーに関する表示も必ず確認するようにしましょう。
砂糖や塩分の量をチェック
砂糖の摂りすぎは虫歯や肥満などのリスクがありますし、塩分過多も将来的な病気のリスクになります。
原材料をチェックしたあとは、成分表で糖質と塩分量だけでも目を通してみるといいですね。
1日の砂糖の摂取目安量は、厚生労働省の食事摂取基準に基づくと以下の通りです。
【砂糖】
1歳~2歳児:約5g
3歳~5歳児:約7g
【塩分】
1~2歳:男子3.0g未満、女子3.0g未満
3~5歳:男子4.0g未満、女子4.5g未満
かりんとう1本で砂糖1g、マシュマロ1つで約2gですから、気をつけないとあっという間に1日の目安量を超えてしまいますよ。
喉への詰まりやすさ、形状をチェック!
子ども向けに作られている市販のお菓子は、形状にも配慮されているものが多いですが、赤ちゃんのお菓子の定番ともいえるボーロも最初から上手に食べられるとは限りません。溶けるように作られていますが、食べているときは赤ちゃんが食べている間は、そばを離れずに様子を見てあげましょう。
小さいもの、丸いもの、硬すぎるものなどは要注意です。
一方で、市販のお菓子は、カリッ、サクッとした食感をはじめ、3度の食事だけでは体験できない味覚や食感の体験ができるというメリットもありますから、
「空腹を満たすためのものではなく、心の栄養として」
を念頭におきながら、量や頻度に気をつけ、上手に付き合いましょう。
何を選べばいいの? と迷ったときは……
市販のお菓子は大きく分けて「乳幼児用」につくられたものと、大人も食べる一般的なお菓子がありますよね。
原材料のチェックなどが難しい、よくわからない、などと迷ったら乳幼児用の表記のあるものを選ぶと安心です。乳幼児向けのお菓子は、添加物や糖分、塩分などが控えめに調整されているものが多く、形状や硬さも、お子さんが食べやすいように工夫されていますよ。
一方で、子ども用のお菓子のイメージが強い駄菓子は、着色料が使われているものが多いのでなるべく控えましょう。着色料の過剰摂取はアレルギー症状を引き起こす原因になることもあるので、要注意です。
【種類別】食べ始め時期と注意点

チョコレート
【いつから? 】
できる限り砂糖が入ったお菓子は3歳まであげるのを控えましょう。
難しい状況もあるかもしれまえせんが、3歳をひとつの区切りとして意識してみてください。3歳というのは判断力も少しついて、物事の良し悪しが理解できる年齢です。
また、集団生活を経験する年齢なので、そのなかで少しずつ、慎重に考えてみてくださいね。
【注意点】
カカオマスにはカフェインが含まれているので、興奮作用があります。乳幼児の睡眠を妨げる可能性は否定できません。少量でも、糖分・脂肪分の摂取量が小さい子どもにとっては過多になりやすいので、注意しましょう。虫歯や肥満の原因にもなります。
グミ
【いつから?】
一般的に、4歳以降とされています。
【注意点】
弾力があり、喉に詰まらせる可能性があります。かむ力が十分に身につくまで、誤えんを招く可能性があるので控えましょう。糖分も非常に多く含まれるため、虫歯の原因となりやすいです。 また、着色料や香料などの添加物が含まれているものが多いので気をつけましょう。
ケーキ
【いつから? 】
手作りの場合は、糖質脂質などをコントロールできるので1歳頃から与えられる場合もありますが、市販のケーキは2〜3歳以降にしましょう。
日常的にあげるのではなく、お誕生日やクリスマスなどの特別なイベントのときにあげるなどの工夫をしましょう。
「特別な日」があるというのも子どもにとっていいことですね。
【注意点】
砂糖や生クリーム、バターを多く含むケーキは、消化に負担をかけます。大量生産されているケーキの場合は、着色料や保存料などの添加物が含まれる場合がありますし、ケーキ屋さんのものは原材料・成分表を確認できないのでなるべく遅めの食べ始め時期を心がけましょう。
せんべい
【いつから?】
赤ちゃん用のせんべいは、離乳食時期から与えられるものもあります。 ただし、一般的なせんべいは、塩分が高いものが多いので2歳以降、少量ずつを目安にしましょう。
【注意点】
一般的なせんべいは塩分が多く、乳幼児の腎臓に負担をかけます。えび味などアレルギーに注意が必要な味付けも少なくないので、なるべく3歳未満では子ども用のせんべいを選ぶようにしましょう。かむ力も養われてからにしましょう。
スナック菓子
【いつから?】
できる限り与えはじめは遅いことにこしたことはありませんが、製品の幅が広く、子ども用のスナック菓子は1歳から食べられるよう脂質や塩分を押さえたものもあります。
【注意点】
一般的なスナック菓子は、乳幼児の腎臓に負担をかけますし、高脂肪で、おやつの時間に与えると、その後の食事が十分に摂れなくなる可能性があります。添加物が含まれているケースも多いので、未就学児の頃はなるべく子ども用のものを選びましょう。もしも一般的なスナック菓子を選ぶなら、大豆が使われているなど、材料が配慮されているものを選びましょう。
ハンバーガーなどのファストフード
【いつから?】
なるべく3歳以降の摂取にしたいところです。
【注意点】
ファストフードは、手軽に食べられる一方で、高カロリー、高脂肪、高塩分の傾向があります。
幼児期に必要な栄養素は、バランスの取れた食事から摂取するのが基本ですから、たまにならよいですが頻繁な摂取は控えましょう。
消化に負担をかけ、将来的な肥満や生活習慣病のリスクを高めてしまうことも考えられます。
「ケチャップぬき」「ポテトに塩はかけない」などオーダーの仕方に工夫をしてみるといいですね。
体の栄養と心の栄養を分けて考えましょう!

この記事では、お子さんのおやつデビューの時期や、おやつを選ぶ際のポイント、注意したい市販のお菓子やファストフードについて解説しました。
おやつは、お子さんの成長に必要な栄養を補給する大切な役割を持つ一方で、与える時期や内容、量によっては、健康に悪影響を与える可能性もあります。
この記事の著者編集部Jも2児の母ですが、次男の子育ての際、つい長男と同じおやつを与えることが多々ありました。
いまでは大きくなり、それがのちの2人の体格や健康に影響してしまったかも…と思うことがあります。
大変な育児のなかで市販のおやつを取り入れるのが悪いわけではありません。
正しい知識をもって、上手に付き合えるといいですね! というご提案です。
フルーツや野菜を切っただけ(もちろんお子さんの成長にあわせたかたさで)でも立派なおやつ。
無理ない範囲でお子さんのためにできることを、ぜひ考えてみてくださいね。
見落としがちなことに、飲料があります。ジュースにも糖分が含まれていますし、牛乳コップ1杯で満腹になってごはんが進まないといったこともあります。
飲料についてもおやつのじかんを守って摂取するようにしましょう。
この記事を参考に、お子さんの成長と発達に合わせた、安全で楽しいおやつタイムを過ごせますように。
【監修】岡本正子先生
管理栄養士・国際薬膳師。東京生まれ。明治大学第二文学部卒業。3人の子育てをしながら栄養学を学ぶ。矢島助産院で日々、妊婦さんや産後ママのための食事を担当する傍ら、企業や雑誌などで離乳食の監修やママのための食に関する講演・講習会などを各地で行う。著書に『妊娠・授乳中の気になる症状改善レシピ200』(日東書院)、『子どもが元気に育つ毎日の簡単ごはん』ほか
※アレルギーをお持ちのお子さんには、記事中に記載してある注意事項以外にもアレルギーについてのご配慮をなさってください。
参照:
農林水産省「子どもの食育〜おやつの工夫」