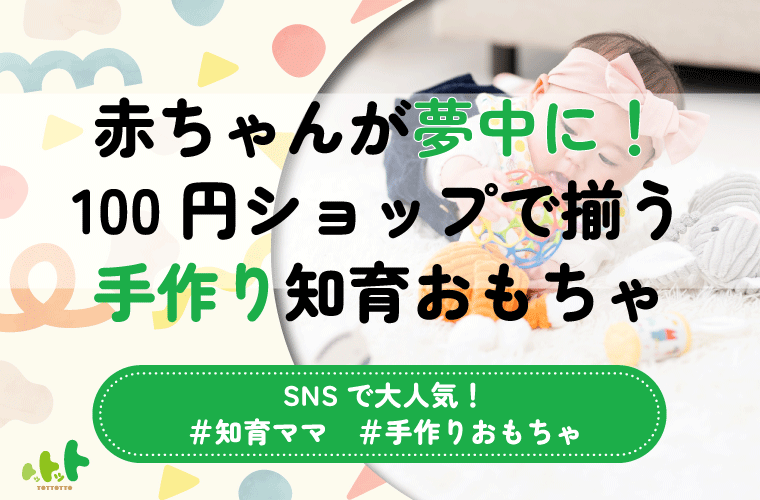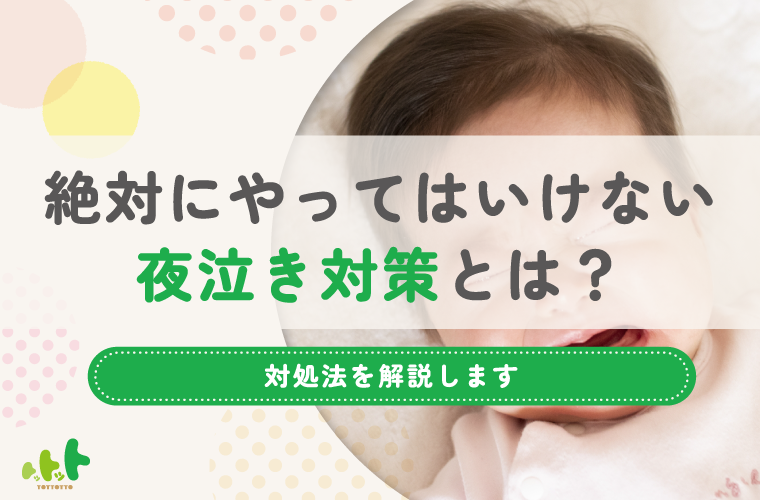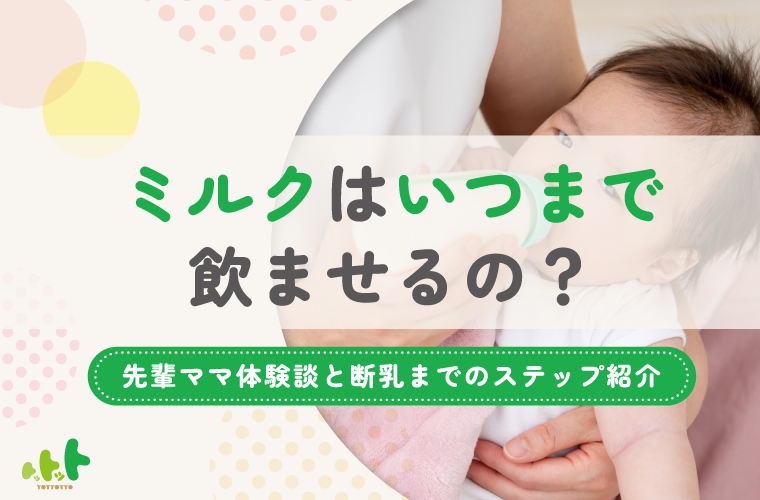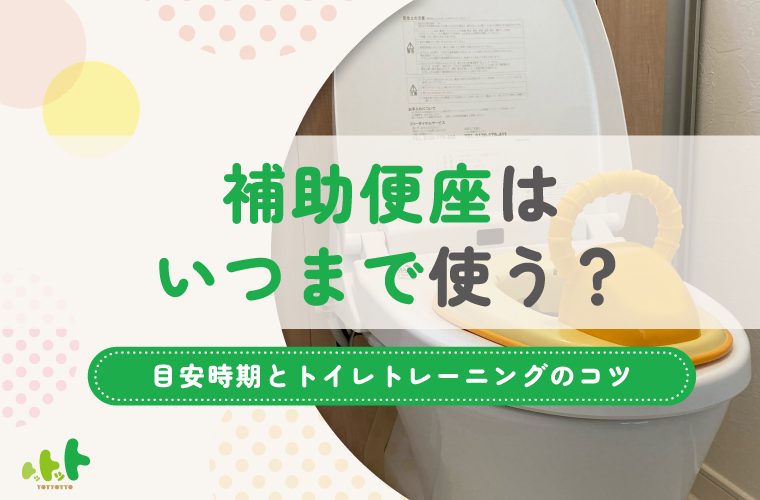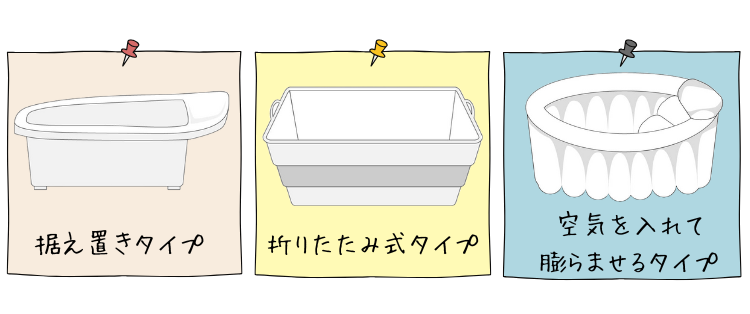赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て
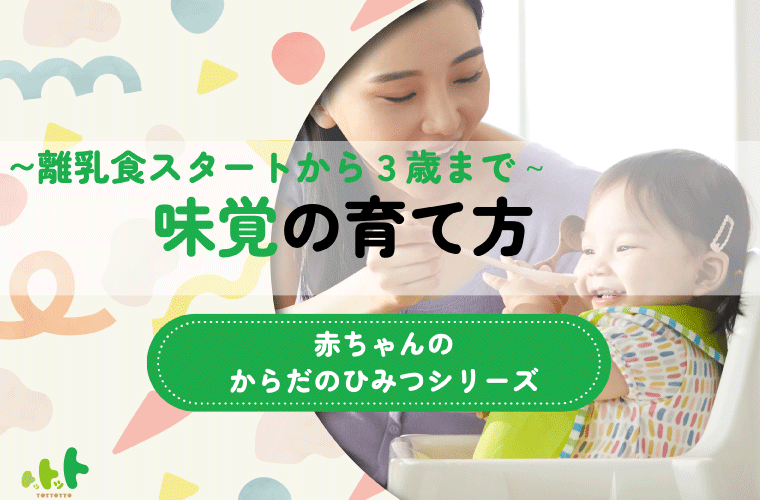
「せっかく作ったのに食べてくれない…」
「もしかして、離乳食がおいしくないから?」
「好き嫌いをするけれど大丈夫?」
お子さんの食事について、そんな悩みや不安を抱えているママ&パパへ。
味覚は、私たち人間がもつ五感の中でも、食事の楽しさを大きく左右し、人生をゆたかにしてくれる大切な感覚です。
赤ちゃんの味覚は、生まれたときから驚くべき可能性を秘めています。年齢に合わせた食育で、子どもの味覚を豊かに育てましょう。
この記事を読めば、いつもと違った新しい視点で離乳食をとらえられるかもしれません。
お子さんの味覚を豊かに育てるヒントをご紹介していきますね。
10年以上子どもの食にまつわる連載をしてきた編集部Jがお届けします!
味覚を育てるってどういうこと?

自分が好きなおやつを食べるときのことを想像してみてください。
甘いデザートを思い浮かべた人、ポテトチップスやおせんべいなどのしょっぱいものを想像した人、さまざまでしょう。
味の好みは人それぞれ。そんな「好み」に大きく影響しているのが、子どもの頃の食生活です。
そしてそれは、赤ちゃんの頃からはじまっています。
食のスタートとなる離乳食の役割には、
- 母乳やミルクだけでは補いきれなくなる栄養の補給
- 新しい味と出会い味覚を養う
- 食べるための練習(かむ力、飲みこむ力をつける)
- 食べることの楽しさを知る
などがあげられます。
「新しい味と出会い、味覚を養う」ことも大切な離乳食の役割のひとつなんですね。
でも実際に味覚って、どうやって育ててあげたらいいのでしょう?
知ってる?味覚のセンサー味蕾(みらい)について
について.jpg)
味覚を育むためにまず知っておきたいのが、味を感じる仕組みです。
「おいしい!」と感じるとき、私たちの体の中では一体何が起こっているのでしょうか?
実は、舌の上には味蕾と呼ばれる小さなセンサーがたくさんあって、その味蕾が味を感じとる重要な役割を果たしているんです。
この味蕾で、甘い、しょっぱい、苦いなどさまざまな味を感じます。味蕾は赤ちゃんがお腹のなかにいるときから形成されはじめています。
赤ちゃんの味蕾は、大人よりも多い!?
舌にある味蕾の数は数千から1万個以上ともいわれていますが、実はこの数、大人より子どもの方が多いんです!
大人になるにつれ減少していき、味覚も鈍くなってきます。つまり、味蕾の数が多い子ども時代のほうが「味に敏感」なんですね。
「子どもの頃は苦いものが食べられなかったのに、大人になって食べられるようになった」といった話を聞いたことがあると思いますが、その要因のひとつは、味覚がにぶくなって苦味を受け入れられるようになるからといった説もあるほどです。
赤ちゃんの体は大人になるにつれ発達していく部位が多いのに、味覚は大人になるにつれ減退していくというのですから不思議ですね。
子どもの味覚は大人よりも繊細で敏感と聞くと、いっそう乳幼児期の「味わい」について考えてあげたくなりますね。
五味からなる味〜好き嫌いのひみつ

「味」のひみつをさらに深掘りしていきましょう!
私たちの舌は、甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5つの基本味(五味)を感じることができます。これらの味は、それぞれ異なる役割を持ち、私たちの食生活に欠かせない要素です。
甘味
●エネルギー源となる糖質を感知します。
●赤ちゃんが最初に知る味、母乳も甘味の代表的な味です。
●赤ちゃんは、生まれたときから甘味を好む傾向があります。
塩味
●体内のミネラルバランスを調整します。
●過剰摂取は、高血圧などの原因となるため、注意が必要です。
●赤ちゃんは、本能的に「おいしい」と感じます。
酸味
●食品の腐敗や未熟さを感知します。
●酸味は、食欲を増進させる効果もあります。
●赤ちゃんに与えようとすると「まずい」と感じるため拒絶します。
苦味
●毒物や有害物質を感知します。
●赤ちゃんは、苦味を嫌う傾向があります。
●苦味は毒素を示すシグナルであるため、赤ちゃんは「まずい」と感じ、拒絶反応を示します。
●これは動物も同様に示す、生きていくための防衛本能です。
うま味
●たんぱく質を感知し、食欲を増進させます。
●うま味は、昆布やかつお節などに多く含まれています。
●赤ちゃんは、本能的に「おいしい」と感じます。
赤ちゃんは、生まれたときから甘味を好み、苦味を嫌う傾向があります。これは、単なる好き嫌いではなく、生きていくための本能によるものです。
苦い味は、自然界では毒のあるものによくある味。だから、赤ちゃんは苦い味を「危ない!」と感じるようにできています。赤ちゃんが自分の身を守るための本能なんですね。ですから、離乳食時期に食べてくれないといってあまり悩まなくても大丈夫!
何度も繰り返し体験するなかで食べてくれるようになることがほとんどです。
成長とともに味覚は発達し、さまざまな味を受け入れられるようになります。離乳食を通して、少しずつ色々な味を体験させてあげましょう。
味覚を育むステップ〜離乳食と五味
離乳食は、赤ちゃんが五味を体験し、味覚を育むための大切なステップです。味覚の発達段階に合わせて、五味をバランスよく体験させてあげましょう。
あまり食べてくれないな…という食材は、体験させてあげるタイミングを工夫すると食べてくれるようになることも!
離乳食初期(5~6ヵ月ごろ):甘味・うま味体験
:甘味・うま味体験.jpg)
赤ちゃんが最初に口にする味、母乳は自然な甘味を持っています。そのため、離乳食も甘味のある10倍粥からスタートし、甘味に慣れ親しんでもらいましょう。
次に、昆布や野菜などでだしを取り、うま味を体験させてあげましょう。うま味は、母乳や羊水にも含まれる赤ちゃんにとってなじみ深い味です。お粥に出汁をプラスするだけでも赤ちゃんにとってはごちそうです!
この時期は特に、素材そのものの味を活かしたシンプルな調理を心がけましょう。
ほうれん草やブロッコリーなどの野菜も初期からOKとされている食材ですが、苦味はまだまだ苦手な時期。あせる必要はありませんよ。あげる際は、茹でるなど加熱する調理法で苦味を和らげる工夫が大切です。嫌がったら無理強いするのはやめましょう。
離乳食中期(7~8ヵ月ごろ):塩味・酸味体験
豆腐や白身魚など、たんぱく質を取り入れ、素材そのものの塩味を体験させてあげましょう。
ヨーグルトや柑橘類などで、酸味の体験もこの時期におすすめです。酸味は、食欲を増進させる効果もあります。
少しずつ、さまざまな食材を組み合わせて味のバリエーションを体験させてあげてくださいね。
離乳食後期(9~11ヵ月):五味を組み合わせた味の体験

手づかみ食べの練習も始め、いろいろな食感を体験させてあげましょう。
食感は、味覚に大きな影響を与えます。たとえば、同じ食材でも、すりつぶしたものと角切りにしたものでは、味の感じ方が異なります。
ザラザラ、ツルツル、シャキシャキなど、さまざまな食感を体験することで、味覚がより豊かに発達します。
いろいろな食感を体験することは、かむ練習にもつながりますよ。
また、「野菜の苦味などはまだ苦手みたい…」というときなども、五味を組み合わせた「食感」の体験がおすすめです。
たとえば、「ほうれん草と豆腐のあえもの」などは、すりつぶした滑らかな豆腐の食感のなかにみじん切りしたほうれん草の存在を感じながら、味覚と食感のハーモニーを楽しむことができますよ。
酸味が苦手なら、バナナとヨーグルトを組み合わせたり、かぼちゃペーストとにみじん切りのりんごを混ぜたりといった具合です。
薄味を基本に、さまざまな食材を組み合わせてみましょう。
離乳食完了期(1歳~1歳6ヵ月ごろ):味覚の多様化
:味覚の多様化.jpg)
後期の延長として、さまざまな食材の組み合わせを楽しませてあげましょう。
後期のころよりは少しずつ苦味や酸味を受け入れやすくなってきますが、まだ焦らなくて大丈夫ですよ。うま味を使いながら五味のバランスを意識するといい時期です。
たとえば、甘味のある果物と酸味のあるヨーグルトを組み合わせたり、苦味のある野菜と旨味のあるだしを組み合わせたりすることで、味覚の幅を広げることができます。
歯も増えてきているので、かむことの楽しさも一層増しますよ。
幼児食期(1歳6ヵ月〜3歳ごろ):苦味に慣れる
野菜などに含まれる苦味も繰り返し体験させてあげましょう。苦味は、毒物を感知するための味覚ですが、少しずつ慣れることで、野菜嫌いの予防にもつながります。
ただし、嫌がったら決して無理強いしないことがポイントです。
家族みんなで食卓を囲み、楽しい雰囲気の中で食事をすることで、おいしい!と感じられることもあります。
季節の食材を取り入れたり、盛り付けを工夫したりすることも、食欲をそそり、苦手な味を受け入れやすくなります。
3歳頃にはほとんどの味覚が発達するとも言われ、10歳ぐらいまでに味の好みも確立してきます。
味覚を育むためのポイント

赤ちゃんの味覚を豊かに育てるために、特に大切な3つのポイントがあります。
難しく考える必要はありません。毎日の食事で少し意識するだけで、お子さんの未来の食生活が大きく変わりますよ。
うす味を心がける
- 最初は食材の味そのものを体験させてあげましょう。
- 赤ちゃんの味蕾は敏感なので、うす味でも十分おいしく感じます。大人の味覚で「ちょっとうすいかな?」と感じるくらいでいいでしょう。
- うま味を利用すると、うす味でもおいしく! しらすやパン、うどんなど、食材そのものにも塩分などが含まれているものがあるので、その味を活用しましょう。
- 濃い味付けは、味覚の発達を鈍らせ、将来の生活習慣病のリスクを高める可能性もあるので注意しましょう。
いろいろな食材を試す
- 色々な食材を組み合わせ、五味をバランスよく体験させましょう。
- 赤ちゃんの舌にある味蕾は、さまざまな味を体験することで発達していきます。 色々な食材を試すことは味蕾を刺激し、味覚の発達を促すための大切なトレーニング です。
- いろいろな食材を試すことは偏食予防にも繋がり、将来好き嫌いの少ない子に育つ可能性も高まります。
食事の環境を整える
- 楽しい雰囲気で食事をすることで、子どもの食欲もアップ! おいしく感じやすくなります。
- 食事の環境を整えることは、単に食欲を増進させるだけでなく、子どもの 心と体の成長 にもいい影響を与えます。
- 食べているときに「甘いね〜」「ちょっと苦かったかな?」「やわらかいね、とろけそう!」などと子どもが体験していることを言葉にしながら声がけしましょう。体験がそのまま言葉に置き換えられることはとても大切です。さまざまな味の表現を聞くことで、子どもは味覚の多様性に気づき、新しい味への興味をもつようになりますよ。
味覚と食育Q&A

赤ちゃんの味覚は、生まれたときから驚くべき可能性を秘めています。離乳食の進め方や味覚に関する疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。
Q:離乳食の味付けはいつから始めるべき?
A:離乳食初期から中期はまだ、なるべく調味料には頼らずに食材そのものの味を体験させてあげましょう。大人の食事から取り分ける場合は、必ず味付け前のものを使用してください。赤ちゃんの味覚は大人よりも敏感で、内臓機能も未発達なため、濃い味付けは負担になります。
Q:赤ちゃんが酸味や苦味を嫌がります。どうすればいい?
A:酸味や苦味は、赤ちゃんにとって本能的に避けたい味です。無理強いせず、成長に合わせて少しずつ慣らしていきましょう。調理法を工夫したり、ほかの食材と組み合わせたりするのも効果的です。たとえば、トマトは煮込むと酸味が和らぎ、ほうれん草はだしをきかせると食べやすくなりますよ。
Q:かむことと味覚の発達には関係があるの?
A:食べ物をしっかりかむことで、味を感じやすくなります。舌の動きや歯の本数も関係するため、赤ちゃんの成長に合わせて食材の固さや形を調整しましょう。よくかむことは、唾液の分泌も促します。唾液は、味蕾を保護し、清潔に保つ役割も担っているので、味蕾の機能を正常に保てることにつながります。
Q:味覚を育てることのメリットは?
味覚を育てることは、子どもの食生活や健康に多くのメリットをもたらします。
たとえば、
好き嫌いが減る
さまざまな味や食感に慣れ親しむことで、偏食が改善され、好き嫌いが減ります。
健康的になれる
自然とうす味を好むようになり、濃い味付けの食品や甘いお菓子への依存が減ります。さまざまな食材からバランス良く栄養を摂取できるようにもなるので、健康的な食生活を送ることができます。結果的に、将来的な肥満や生活習慣病のリスクを低減する効果も期待できます。
食事の楽しみが生きる活力につながる
味覚が豊かになることで、食事の時間がより楽しいものになり幸福度が増します。
味覚の黄金期を大切にしよう!

離乳食期〜3歳までの味覚についてご紹介してきました。
赤ちゃんは成長とともに味覚の感受性も変化していきます。特に、離乳食が始まる頃から幼児期にかけては、さまざまな味を経験することで、味覚が発達する大切な時期。この時期を「味覚の黄金期」と呼びます。この黄金期の食生活は将来の食習慣にも大きく影響する大切な期間とされています。
毎日お子さんに食事の準備をするのは大変なことだと思います。毎日を完璧にする必要のありません。ただ、この味覚について知っておくと、「うす味を心がけよう」「いろんな味を体験させてあげよう」と、毎日の食の支度にちょっとした変化が生まれてくることでしょう。
無理なくそれぞれのご家庭のペースで、ぜひ味覚についても考えてみてくださいね。
【参考文献】
子どもの味覚を育てる: ピュイゼ・メソッドのすべて(紀伊國屋書店)
子どもの味覚を育てる 親子で学ぶ「ピュイゼ理論」(CCCメディアハウス)
三國清三シェフの味覚の授業: KIDSシェフ(小学館)