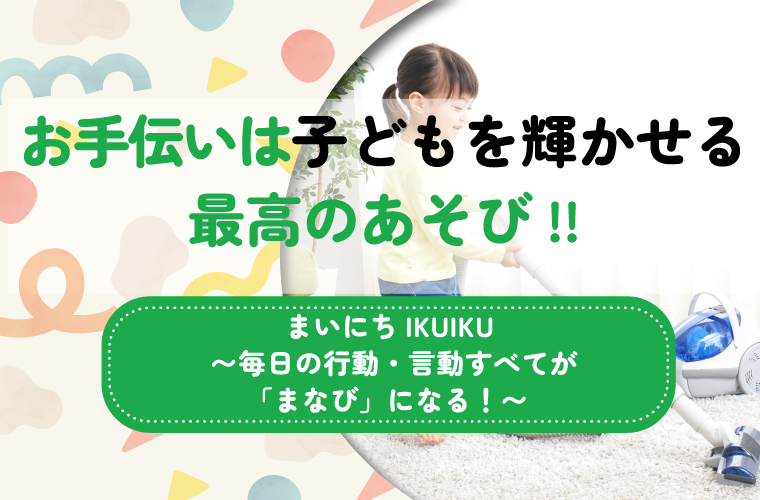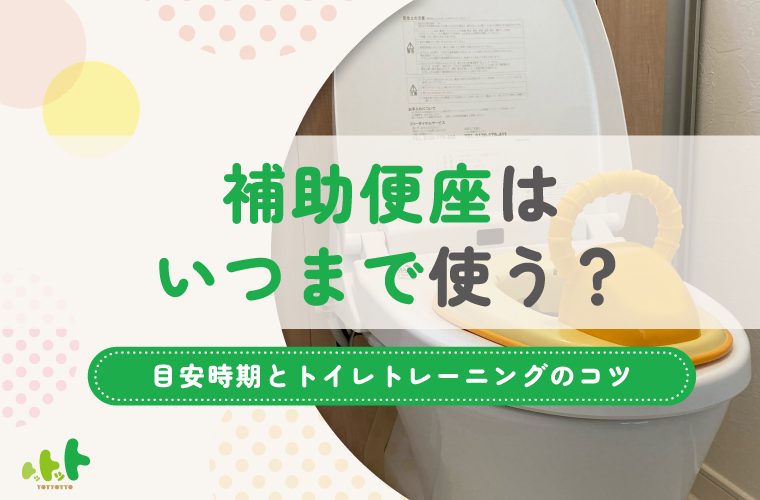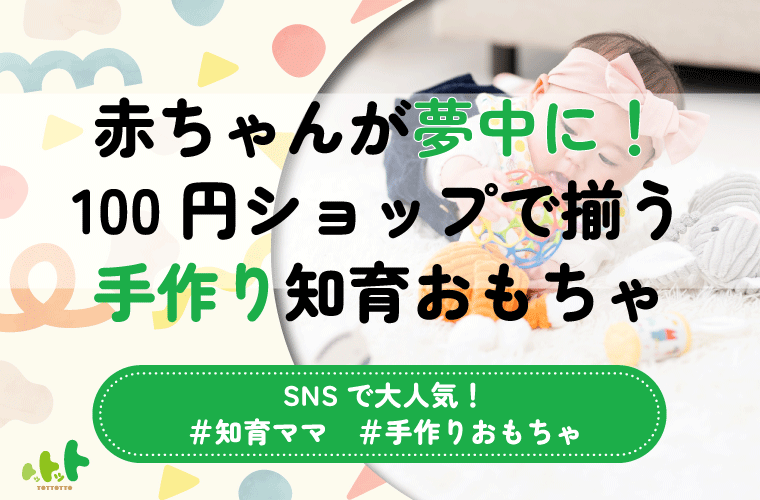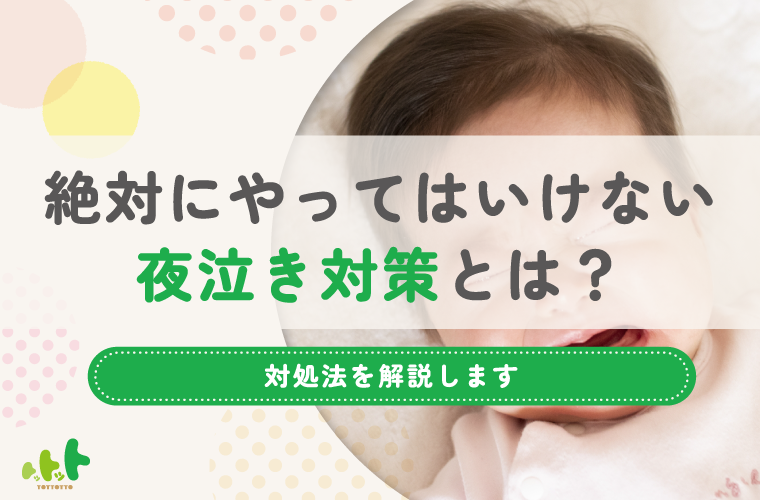赤ちゃん・子育て
赤ちゃん・子育て
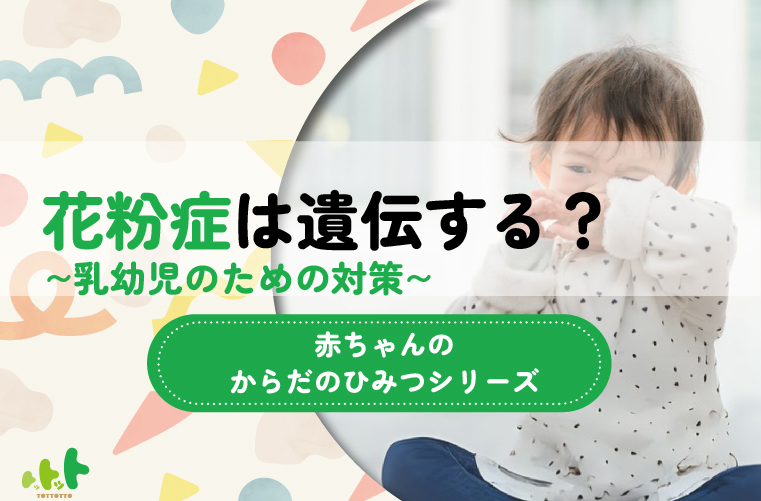
ママやパパが花粉症だと、「子どもにも遺伝するのかな?」と気になりますよね。
ズバリ、花粉症そのものが遺伝することはありません。
でも、花粉症になりやすい「体質が遺伝」している可能性はあります。
ですから、日頃から花粉症を引き起こさないように対策をしていくのがおすすめです。
今回はそんな「乳幼児期の花粉症対策」についてご紹介していきましょう。
編集部Jは2人の子どものママでもありますが、1人は花粉症、1人は花粉症ではありません。
同じように育てていたはずなのに、何が違ったんだろう、と気になっています。
ママ&パパが花粉症じゃなくてもお子さんが発症してしまうケースもあります。
日頃からどんなことに気をつけたらいいのか、ぜひチェックしてみてくださいね。
花粉症はいつから?赤ちゃんでも花粉症になるの?
花粉症は、スギやヒノキなどの植物の花粉を体内に取り込むことで、体が過敏に反応して起こるアレルギーです。遺伝的な要素、環境要因、生活習慣など、いろいろなことが重なって発症します。

環境省の花粉症マニュアルによると、花粉症の有病率は1998年には19.6%だったのに対して2019年には42.5%、つまり2倍にも増えているんです。6〜10歳においてはそれ以上だそう!
※全国の耳鼻咽喉科医とその家族を対象にした全国調査
ですから、赤ちゃんでも油断は禁物。0歳のうちから花粉にふれることはありますし、最近は2~3歳で花粉症になる子も増えてきています。
もちろん、生まれたばかりの赤ちゃんはまだ花粉にふれる機会が少ないので、すぐに花粉症になるわけではありません。
スギ花粉症の割合は、年齢とともに増加しています。
| 0~4歳 | 約3.8% |
| 5~9歳 | 約30.1% |
| 10~19歳 | 約49.5% |
出典:2024年度版(改定第10版)鼻アレルギー診療ガイドライン-通年性鼻炎と花粉症-
花粉症は早期からきちんと対策すると、進行を遅らせたり、症状を軽くしたりできるといわれています。乳幼児期からの適切なケアは、将来的な花粉症の発症リスクを減らすことにつながるんですね。
特に0~4歳は免疫機能がまだ発達段階なので、環境の影響を受けやすい時期です。この時期に適切な対策を行うことで、将来的なアレルギーの発症リスクを下げられる可能性があるんですよ。
だからこそ、ママ&パパが花粉症について正しく知り、対策していくことが大切なんですね。
花粉症になりやすい人の特徴は?

花粉症の主な原因は花粉を体内に取り込むことですが、それ以外にもさまざまな要因が関わっています。
・遺伝的素質
パパやママが花粉症の場合、赤ちゃんもアレルギー体質を受け継ぎやすいといわれています。
・食生活や腸内環境の乱れ
偏った食生活や、腸内環境の悪化は、免疫機能の低下に繋がり、アレルギー症状を悪化させる可能性があります。
・免疫力の低下
免疫力が低下していると、アレルギー症状が悪化することも。夜泣きや生活リズムの乱れなどが、免疫力低下の引き金になります。
・乾燥肌
乾燥した肌はバリア機能が低下し、花粉などのアレルゲンが侵入しやすくなります。特に、乳幼児期はもともと肌のバリア機能が未熟なので、乾燥しやすい状態にあります。
いかがでしょう。気になる項目はありましたか?
ほかにも、都会の空気には地方の空気に比べて、大気汚染物質が多く含まれているためアレルギーを引き起こしやすく、花粉症になりやすいという説もあります。
現代では2人に1人が花粉症になっているともいわれていますし、遺伝的な素質がまったくない人のほうが減ってきています。だれもがなりうる花粉症だからこそ、赤ちゃんのうちからしっかり対策をしていくことが大切なんですね。
早めの対策が大切!がわかる「アレルギーマーチ」

※本図はアレルギー疾患の発症寛解を図示したもので「再発」については示していない。(馬場實氏による原図を参照)
花粉症のほかにも乳幼児がかかりやすいアレルギーはいろいろあります。
食物アレルギー、アナフィラキシー、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎などが代表的でしょう。
実は、これらアレルギーは深い関わりがあることがわかっています。それぞれ別々のものというよりは、アレルギーとしてつながっているイメージです。
上の図は、アレルギーマーチのイメージ図です。
アレルギーマーチとは、赤ちゃんが成長するにつれて、次々とアレルギー症状が現れること。遺伝的にアレルギーになりやすい素質の人が、年齢を経るごとに次から次へとアレルギー疾患を発症するケースが多いことがわかっていて、それを“アレルギーマーチ”と呼んでいます。
例えば、
STEP1)赤ちゃんの頃は肌がカサカサ(乳児湿疹やアトピー性皮膚炎の傾向)
STEP2)少し大きくなると食べ物でアレルギー反応(食物アレルギー)
STEP3)さらに大きくなると鼻水やくしゃみ(アレルギー性鼻炎)
といったように、まるでアレルギーが「行進(マーチ)」していくように症状が変わっていくことから、そう呼ばれています。
花粉症(季節性アレルギー性鼻炎)の発症は年々早まってきているので上の図はあくまでイメージですが、厚生労働省が保育所にアレルギー指導をするときにはアレルギーマーチについての説明も添えているほど大切なことなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
ハウスダストやダニのアレルギー、食物アレルギーがあるお子さんは花粉症になりやすい、さらにさかのぼると、そうしたアレルギー素因は肌から体内に入ることもあるので肌荒れや乳児湿疹にも配慮しておくといいんですよ。
大人と違うの?乳幼児の花粉症「症状チェック」

子どもの花粉症は大人の症状と少し異なって、くしゃみはあまりでません。
また、鼻の穴が小さいため鼻づまりを起こしやすい特徴があります。鼻がつまるのはとてもつらい状態です。口呼吸も増えてしまいます。
「鼻がぐずぐずしているみたい」「ちょっと涙目かしら?」と気になる症状がうかがえると、「風邪と花粉症、どっちだろう?」と疑問に思うこともあるでしょう。
花粉症と風邪との見分け方は?
乳幼児は自分で症状を伝えられませんし、花粉症と風邪は、鼻水やくしゃみなどの症状が似ているため、見分けるのが難しい場合があります。
表を参考に、お子さんの症状をよく観察してみましょう。
| 症状 | 花粉症 | 風邪 |
| 鼻水 | 透明でサラサラ、または粘り気がある | 黄色や緑色で粘り気がある |
| くしゃみ | 出るときは、連続して何度も出ることが多い | ときどき出る |
| 目のかゆみ | ある | ほとんどない |
| 発熱 | ほとんどない | ある場合がある |
比べてみると、かゆみや発熱の違いがわかりやすいですね。
次は花粉症の症状を詳しくみていきましょう。
<子どもの花粉症の症状例>
当てはまる項目が多ければ、花粉症の可能性があります。
☑鼻水・鼻づまり
大人の花粉症の鼻水はサラサラしていますが、子どもの場合は粘り気があるケースもあります。
☑口呼吸
鼻がつまっていると口呼吸になりがち。口をあけてぼ〜っとした様子も要注意です。
☑かゆみ
目をよくこすったり、顔など肌がでているところをよくかきむしっているときは、花粉が付着しているかもしれません。風邪の症状との大きな違いです。
☑目の充血やまぶたのはれ
花粉は、目、鼻、口、肌などから体内に入り込みます。
☑涙目
目に入った花粉を涙でだそうとしている反応です。
☑くしゃみ
鼻に入ってきた花粉などの異物を、勢いよく外に追い出すための体の反応です。
☑いびき
寝ているときにいつもといびきの音が違うと感じたら、鼻がつまっているのかもしれません。
鼻がつまっていると、睡眠の質が低下して日中に眠気を感じやすくなり、結果として注意力や集中力が低下しやすくなることに注意しましょう。また、注意力や集中力の低下により、ストレスやイライラを感じる機会が増えるなどのケースも多く見られます。
赤ちゃんの鼻詰まりは睡眠やストレスにも影響する!

赤ちゃんが鼻づまりで苦しそうにしていると、ママも心配になりますよね。
鼻がつまっていると、おっぱいをうまく吸えなくなったり、夜ぐっすり眠れなくなって、昼間も眠たくなりがちです。
睡眠中は成長ホルモンがたくさん分泌されるので、ぐっすり眠ることも乳幼児の仕事のひとつともいえます。
赤ちゃんも眠たいとイライラしたり、ストレスを感じたりすることがあります。「鼻をかみたい!」という代わりに泣いてうったえるかもしれませんね。
「鼻がつまっているかな?」と感じたら、ガーゼでぬぐってあげたり鼻吸い器をつかって早めに解消してあげましょう。
対処法)花粉はこう防ごう!
花粉症の対策は、第一に花粉になるべくのふれないようにすることです。
花粉症になっていない赤ちゃんも、なるべく花粉との接触をさけましょう。
一般的に花粉対策にはマスクが効果的といわれていますが、赤ちゃんはマスクができないので、次のような工夫をしてみてください。
- 外あそびは、比較的花粉が少ない午前中に!
- 花粉が多い日の洗濯物は、部屋干しにしましょう
- 外出の際は、花粉がつきにくいツルツルした素材の服がおすすめ。帽子も頭に付着する花粉を防ぐのに役立ちます
- 帰宅したら、花粉を払い落としたり服を着替えたりして、花粉を家にもちこまないようにしましょう
- 室内の掃除をまめに行い、換気は花粉が比較的少ない朝に。空気清浄機を活用するのもいいでしょう
厚生労働省の花粉症Q&A集から学ぶ、赤ちゃん対策
厚生労働省の花粉症Q&A集から、赤ちゃんにおすすめの対策をピックアップしました。
Q:顔についた花粉は?
A:花粉が付着しやすいのは表面に出ている頭と顔です。外出から帰ってきたら洗顔をして花粉を落とすといいでしょう。
自分で顔が洗えない0〜1歳の赤ちゃんはガーゼやコットンなどでやさしくふきとってあげてもいいですね。

Q:ヨーグルトは効果がある?
ヨーグルトで腸内環境を整えることは、アレルギー対策になると考えられています。しかし、効果の程度は個人差が大きいようです。
Q:鼻の穴にクリームを塗るのは?
鼻の穴に塗るクリームは、花粉をブロックする効果が期待できます。ただし、薬効成分は含まれていないことがほとんどなので、治療する効果はないでしょう。
2歳以降になったらマスクやうがいを生活習慣に!
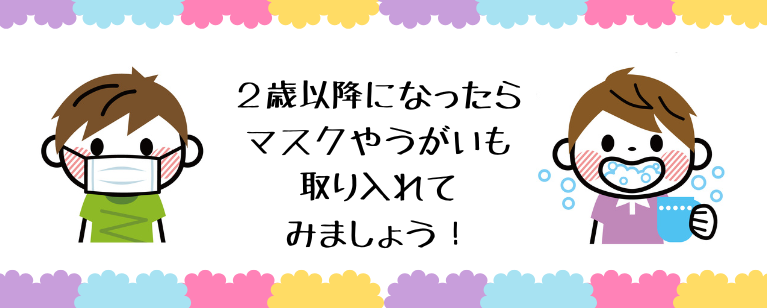
マスクは、花粉の飛散の多いときにはおよそ1/3から1/6に吸い込む花粉の量を減らし、鼻の症状を軽くすることが期待できます。
また、外出から帰ってきたらうがいをする習慣をつけるといいですね。鼻からのどに流れた花粉を除去するのに効果があります。
※2歳未満のお子様へのマスクの着用は推奨されていません。2歳以降のお子様も、マスクの着用は保護者の判断のもと十分に注意して行ってください。夏場の使用も熱中症などへの配慮をしましょう。(厚生労働省子どものマスク着用について)
花粉症は何科を受診すればいい?

赤ちゃんが花粉症のような症状を見せると、ママ&パパは心配になりますよね。くしゃみや鼻水、目のかゆみなどが続く場合は、早めに小児科や耳鼻科を受診しましょう。
どちらがいいの?と迷うところですが、子どもがまだ話せないうちは小児科がいいでしょう。鼻づまりがひどいときは、耳鼻科で吸い取ってくれる場合もあります。アレルギー科を設けているところもありますね。
何科でもアレルギー検査はできますが、低年齢ではっきりとした結果が出ないことがあります。そのため、検査を受けるかどうかは、赤ちゃんの様子を見ながら医師と相談して決めるのがいいでしょう。
受診の際は、以下の点を医師に伝えるとスムーズです。
- いつから、どのような症状が出ているのか
- 症状が出やすい時間帯や場所
- 家族にアレルギー体質の人がいるかどうか
もしかしてそれは「局所性アレルギー性鼻炎」かも?
「うちの子、くしゃみや鼻水が止まらないのに、受診してアレルギー検査をしてもらったけれど何も出なかった…」
もしかしたらそんな可能性もあります。
近年、血液検査や皮膚検査でアレルギー反応が出なくても鼻の粘膜だけがアレルギー反応を起こす「局所性アレルギー性鼻炎」というタイプのアレルギーがあることがわかってきました。
局所性アレルギー性鼻炎って?
- 血液検査や皮膚検査ではアレルギー反応が出ない
- 鼻の粘膜だけがアレルギー反応を起こす
- くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状は一般的なアレルギー性鼻炎と同じ
つまり、一般的なアレルギー検査では見つけられない、隠れたアレルギー性鼻炎といえるかもしれないということなんです。
低年齢のころはアレルギー検査の結果がはっきりしないこともありますので、この局所性アレルギー性鼻炎の可能性もふまえ、根気よく治療をしていきましょう。
赤ちゃんの花粉症は、早期発見・早期対策が大切です。気になる症状があれば、自己判断せずに、まずは医師に相談してみてくださいね。
参考:
環境省「花粉症環境保険マニュアル2022」
厚生労働省「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)」
環境省・厚生労働省「花粉症対策」
厚生労働省「アレルギー性鼻炎・花粉症」